「江戸っ子」ってどんな人? 気質や好み・言葉遣いで知る江戸文化の粋
- 2025/07/15

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
「江戸っ子」という言葉が見られるようになったのは、田沼意次が老中だった頃。明和8年(1771)に作られた「江戸ッ子の わらんじをはく らんがしさ」という川柳が文献上はじめてのものでした。
町人文化が花開く江戸後期を中心に、独特な気質も持つ江戸っ子たちの好みや言葉遣いについて詳しくみてみましょう。
町人文化が花開く江戸後期を中心に、独特な気質も持つ江戸っ子たちの好みや言葉遣いについて詳しくみてみましょう。
そもそも江戸っ子の定義って?
それでは、江戸っ子の定義とは何でしょうか?- 三代江戸に住んだら
- 両親どちらも江戸生まれなら
など、江戸っ子の定義は様々です。基本的には両親が江戸生まれというのが前提となっています。
江戸に住んでいる人々に、「江戸っ子」という意識が生まれたのは、江戸時代後半の頃。地方からの流入者が激増したことが要因だとされています。元から江戸に住んでいる人たちと地方からきた人たちとで区別する…と言ったところでしょうか。
ちなみに、江戸時代後期の歌舞伎・狂言作家である西沢一鳳の著書『皇都午睡(こうとごすい)』には、両親が江戸生まれの「真の江戸っ子」は全体の1割ぐらいしかいなかったと記されています。ちなみに全体の3割を占めているのが、両親のどちらかが地方出身者の「斑っ子」、そして残りの6割を占めているのが、両親とも地方出身でその子供が江戸生まれの「田舎っ子」だったそうです。
一鳳は著書の中で次のように記しています。
最近では、真の江戸っ子ではない田舎っ子が、「オレぁ江戸っ子だ」と騒いでいる…。
江戸っ子が目指したもの…それは「粋」であること
江戸っ子は「粋」であることを良しとしていました。この「粋」というのは、身なりや佇まいが洗練されていて、垢ぬけていること。気質や態度などがさっぱりしていることを表す言葉です。華美になりすぎず、さっぱりとした佇まい。そこはかとなく色気もあり、気が利いている…。これが江戸っ子の理想像といったところでしょうか。

江戸っ子の気質
川柳でみる江戸っ子の気質
江戸に根付いた町人「江戸っ子」。なんと言ってもその大きな特徴は、独特な気質にあります。江戸っ子の性格は、さっぱりしていて、細かいことにこだわらず、金離れが良い。でも時に、短気でせっかち。全員とは言えませんが、江戸っ子にはこのような気質な人が多かったとか。
例えば、こんな川柳が残っています。
「江戸っ子は五月の鯉の吹き流し」
これは、空を泳ぐ鯉のぼりのように、腹の中で何かを企むでもなく、さっぱりしているという江戸っ子の気風(きっぷ)の良さを表現していると言われています。
「江戸っ子の生まれ損ない金を貯め」「江戸っ子は宵越しの銭は持たない」という言葉があるように、江戸っ子はその日に稼いだ金をその日に使いきるという人が多かったと言われています。
ケチケチせず、金ばなれが良いとされる江戸っ子。貯金をしないという人も多かったそうですが、もちろん中にはコツコツと金を貯めている人もいました。「宵越しの金は持たない」ような江戸っ子たちは、それを野暮に感じてしまうそうです。
江戸っ子なのに金を貯めるような人たちを「気質が違う」ということで、この川柳では「生まれ損ない」と表現しています。
「たい焼き」の原型は江戸っ子の気質から生まれた!?
現代でも親しまれている「たい焼き」。一説によると、この形が生まれた要因には、江戸っ子の気質が関係しているとも言われています。もともとは、手で食べれる手軽なおやつとして、小麦粉とあんこでできた丸い形の大判焼(今川焼)が食べられていました。江戸っ子の職人たちも、仕事の合間に栄養補給として食べていたそうです。しかし、江戸っ子は気が短く、中には「手を洗うぐらいなら食べない」人もいたとか。
そこで登場したのが、大判焼の形にヘタ(持ち手部分)をつけたもの。このヘタの部分にはあんは入っていません。これで職人たちは手を洗わず、このヘタの部分を持ちながら食べられるようになったとか。
では、そのあんが入ってない持ち手部分はどうしていたのでしょうか?このヘタの部分は、食べずにそのまま野良犬にあげていたそうです。
諸説ありますが、この「ヘタ付きの大判焼」がのちの「たい焼き」になったとも言われています。
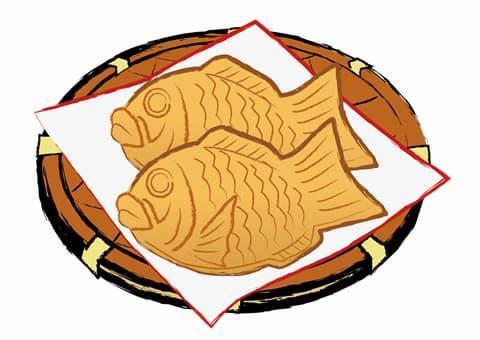
江戸っ子の初物好き
江戸っ子はとにかく初物好き。「初物」とは、その季節ごとに出てきた旬の魚や野菜のことです。日本には古くより、「初物を食べると、七十五日長生きする」という言い伝えがあり、縁起が良いとされてきました。また、誰よりも早く旬の食べ物を食したいという江戸っ子の見栄もあり、江戸時代後期には江戸市内で大ブームになったのです。
その中でも、特に人気だったのが「初鰹」。あまりの人気ぶりから、「女房を質に入れても初鰹」という川柳が詠まれるほどでした。4月から5月頃に水揚げされる初鰹は上等なもので1匹1~3両ぐらいの値段だったとか。1両は現在の価格だと大体10~15万円相当、つまり鰹1匹が約10〜45万で取引されていたということです。
現代の感覚だとあまりにも高価すぎて、びっくりですよね。高価とはいえ、どうしても初物を食べたい江戸っ子たち。そこで多くの庶民は、近所の人たちと共同で初鰹を購入し、皆で分けあって切り身を食べていたそうです。
時代劇などでよく聞く江戸っ子のセリフを解説
江戸っ子が使う言葉は独特なものがたくさん。中には、「時代劇でよく聞くセリフだから聞いたことがある!」という人も多いでしょう。ここでは、江戸っ子がよく使う言葉の意味や由来について解説します。①「べらぼう」
この言葉はよく江戸っ子の間で使われた言葉の1つです。2025年の大河ドラマの題名にもなっていますね。この「べらぼう」とは、「ばか」とか「たわけ」という意味合いを持っています。ちなみに、相手を罵る時は「べらぼうめ」と言い、これは「ばかやろう」という意味になります。
また、この「べらぼう」という言葉には、「異常なほど」や「信じられないくらい」という意味でも使われていました。
例えば、「そいつはべらぼうにたけえぞ」や「昨日の夜はべらぼうに酔った」など様々な場面で使われていました。
②「しゃらくせい」
この言葉も江戸っ子の間でよく使われていました。「分をわきまえず、生意気だ」という意味を持っています。例えば、「餓鬼のくせに、しゃらくせぇことを言うんじゃねぇ!」など子供を叱りつける時にも使われていたようです。
江戸っ子は「分をわきまえる」ことを良しとしていました。だから彼らは「分」、つまり「身のほどを越えた生意気な振舞い」をすることは野暮だと考えていたのです。
③「ちゃきちゃき」
これは「血筋にまじりけがなく生粋であること」や「正統である」という意味を持っています。この言葉の由来となっているのが、「嫡々(ちゃくちゃく)」という言葉。武家では家督を継ぐ子供を「嫡子(ちゃくし)」と言います。そして嫡子から嫡子へと代々家を継いでいくことを「嫡々」と言ったそうです。
この「ちゃくちゃく」という言葉が訛って「ちゃきちゃき」という言葉に変化したと言われています。つまり、「ちゃきちゃきの江戸っ子」というのは、「真の江戸っ子」、「生粋の江戸っ子」という意味になりますね。
おわりに
いかがでしたでしょうか?こうしてみると、「江戸っ子」の定義や、気質を見てもなかなか興味深いところがたくさんありますね。こうした江戸っ子たちが、江戸時代後期の町人文化を発展させてきました。また、彼らは自分たちが江戸っ子であることを誇りに思っていました。垢抜けていること、そして何より粋であること。彼らはそれを意識しつつ、さっそうと江戸時代を生き抜いていったのです。
【主な参考文献】
- 諏訪春雄『江戸っ子の美学』(日本書籍、1980年)
- 中村整史朗『江戸っ子学・知ってるつもり』(大和出版、1994年)
- 中江克己『なぜ江戸っ子を「ちゃきちゃき」と言うのか』(PHP研究所、2008年)
- 若水俊『江戸っ子気質と鯰絵』(角川学芸出版、2007年)


コメント欄