【べらぼう】「一俵の米があっという間になくなる…」 江戸時代の庶民の食生活、小説家・坂口安吾氏の発見とは?
- 2025/07/14
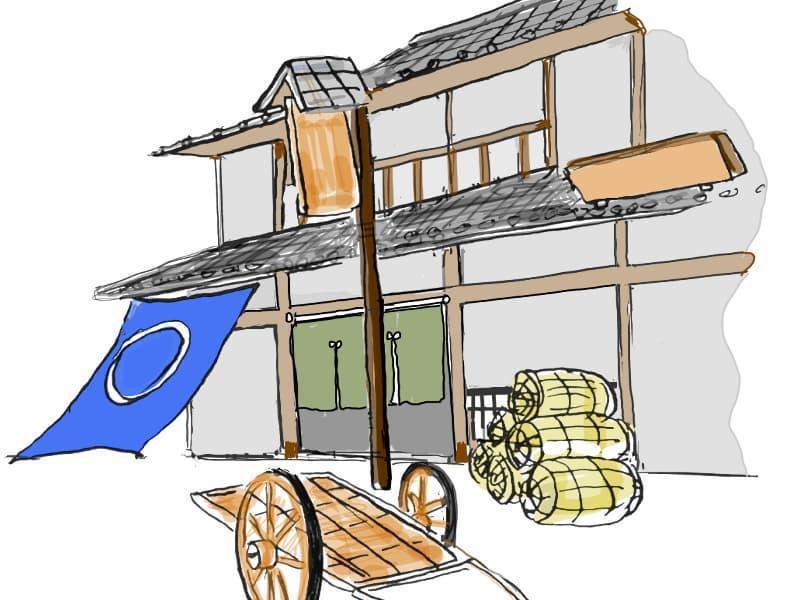
- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
現在、放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう」の中で、主人公の蔦屋重三郎が大店を構え、大勢の使用人を使うようになってから「一俵の米があっという間になくなる」と嘆く場面が出てきます。実際に使用人達も含めた食事のシーンでは、お膳の上に大盛りの米茶碗と味噌汁椀と小皿しかなく、今でいう「おかず」が全く出ていないことが分かります。
大河ドラマでは慎重な歴史考証がなされており、この光景は実は正確なものなのです。実際のところ、当時の江戸の食生活はどのようなものだったのでしょうか?
大河ドラマでは慎重な歴史考証がなされており、この光景は実は正確なものなのです。実際のところ、当時の江戸の食生活はどのようなものだったのでしょうか?
「雨にも負けず風にも負けず」
この表題は皆さんもご存じであろう、宮沢賢治の有名な詩です。その中に「1日に玄米四合と味噌と少しの野菜を食べ」とあるのをご存じでしょうか?現代では一人暮らしの家庭でも1日に四合という大量の米を炊くことはまずありません。実際に自分で炊飯をしたことのある方なら「四合は食べすぎじゃ…」と思われるかもしれません。私自身の経験からも1回に四合もの米を炊飯したことはなく、せいぜい三合です。四合も炊いたら、とても一人では食べきれません。それなのに宮沢賢治は「1日に四合」だと言うのです。この差は一体なんなのでしょうか?
”雨にも負けず風にも負けず”、は宮沢賢治の理想像を描いた詩であると考えるのが妥当です。つまり、1日に四合というのは、実は宮沢賢治の感覚からいうと、質素なものでした。それはこの言葉に続く「味噌と少しの野菜を食べ」という内容でも推し量ることができます。
実は宮沢賢治が生きた戦前に公布されていた徴兵令では、兵士一人あたり「1日に六合の米」を食べさせることになっており、一般的な商家でもそれくらい消費していたようです。肉体を酷使する漁業では出稼ぎ漁師に、1日に八合の米を食べさせることが雇う条件でもあったそうです。こういった人達から比べれば、1日に四合は控えめな量であり、宮沢賢治には質素な生活を表す言葉だったのです。
江戸時代から明治・大正・昭和初期の商家においては、使用人に1日五~六合の米を食べさせるのが当たり前で、一方のおかずは沢庵数切れと味噌汁だけでした。つまり、戦前の食生活は少ないおかず(だいたい漬物)と味噌汁と大量の米を食べることだったのです。
たんぱく質とビタミンの補給は?
不足していたたんぱく質
沢庵数切れと味噌汁とお米だけでは明らかに、たんぱく質が不足します。味噌汁の中には豆腐や挽割納豆を入れることが多かったため、大豆から植物性たんぱく質が摂取できますが、それでも十分とは言えません。その結果、江戸時代の人々の身長は低く、平均で男性で157センチ、女性で145センチだったようです。もっと時代を遡る古墳時代には男性 で163センチ、女性で151センチと推定されており、江戸時代になってから時代を逆行するように平均身長は低くなっていきます。
この傾向は明治時代まで続きました。江戸時代の江戸庶民にとって、魚介類を食べるのは大晦日などの特別な日に限られていたのです。
江戸患いと江戸人の好物
現代の時代劇でも、時々「江戸患い」という、いわゆる「脚気(かっけ)」が主題として取り上げられることがあります。ですので、ビタミンB1の欠乏症であることは、よく知られており、その原因が玄米であれば米ぬかに含まれているビタミンB1が白米に精製されることによって削り取られてしまうことにありました。何故、わざわざ玄米を白米に精製して食べていたのか?それはその方が美味しいからです。実際、地方から小僧が丁稚奉公で江戸にやってくると、白米の美味さに驚いたようで、それをたくさん食べたがるのは当然のことでした。
江戸でも米を買うときは玄米しか売っていないので、「つき屋」と呼ばれる白米の精製業者に、その日食べる分の米を精米してもらい、食べていました。白米を食べることは「江戸っ子の誇り」でもあったようです。しかし地方では、精米する手間なんてかけません。このため、江戸患いの人が地方に旅行すると、玄米を食べることになりますので、江戸患いは一発で治ってしまったそうです。
一人あたり五合の米とは?
一合はおよそ150グラム、五合だと750グラムです。そして江戸時代の一俵の米は、およそ60キログラムとされています。蔦屋重三郎の店では家族、使用人も含めて10人くらいですので、1日に消費する米は最低でも750グラムの10倍として、7.5キログラムとなります。60キログラムをこれで割ると「8日」、つまり蔦重の店では一俵の米が8日で無くなってしまう事になりますね。もし家族の中にたくさん食べる人がいたら8日も持たなかったでしょう。大食らいが数人いれば、5日程度で無くなっても不思議ではありません。
なるほど、「一俵の米があっという間になくなってしまう」という表現は正しいのですね。なんせ蔦重クラスの店ですら、月に4俵から6俵の米が確実に消化されていたのですから。しかも米代だけではなく、江戸では白米が当たり前であり、つきやに頼んで精米してもらう必要もあるため、その費用もかかりました。江戸の店主にとって、米は頭の痛い大問題だったのです。
特に吉原の女郎屋では多くの人数を養っていましたので、それだけ多くの米が消費されていました。おそらく3日くらいで一俵がなくなってしまったのではないでしょうか。吉原では女郎の朝食は白米だけだったため、皆「こうこ屋」から自腹を切って漬物を買い、おかずとして食べていたそう。
味噌汁や、少ないながらも漬物が付く商家の食事は吉原の女郎達に比べれば、まだましな物と言えたのです。
坂口安吾の発見
戦前から戦後にかけて活躍した作家に坂口安吾氏がいます。彼は堕落論などで知られていますが、長崎のキリシタンの歴史に興味を持ち調べていました。江戸時代は家康による禁教令によってキリスト教信仰が禁止されていたため、長崎のキリシタンは常に迫害を受けており、その歴史を調べていたのです。そんな坂口安吾氏があることを不思議に思います。それは捕まったキリシタンの農民が、拷問では全く寝返らないのに「食事の量が少ない」事には耐え切れず、寝返ったという事実でした。しかも幕府側は食事の量で責める気は全く無く、当時としては普通の量を食べさせていたつもりだったようです。
これが安吾氏には不思議に思え、長年の疑問となっていましたが、実際に安吾氏が長崎に行ってチャンポン屋に入ったことで解決することができました。
安吾氏:「長崎に着いて少し小腹が減ったので何か食べることにした。こういう場合、長崎ではチャンポン屋に行くのが当たり前だそうなので、私もチャンポン屋に入ることとする」
チャンポン屋に入った安吾氏の前に、バケツに一杯くらいの量のキャベツと麺が出されたそうです。さらに、他の色々な野菜や肉を煮込んだうま煮を、その上にどろっとかけてくれたのだそうです。その内容と量の多さに安吾氏は
安吾氏:「うーん、もしかすると、この女給の脳は長崎の原爆でおかしくなってしまっており、私が人間ではなく、牛か豚に見えたのではないだろうか?」
と。しかし店に母親とその娘らしき2人連れが入ってきて、その2人の前にも安吾氏と同じものが出されました。そこで安吾氏は考えます。
安吾氏:「なるほど、やはりこれは人間の食べる物らしい。けれど、これを一度に食べられるわけがない。つまり、これを一日、何回かに分けて食べるのではないだろうか?」
しかし、安吾氏がそう考えている間に、なんとその母娘の2人連れは、あっという間に、それを食べ終わって店を出て行ってしまいました。これで安吾氏は了解します。
安吾氏:「そうか! 長崎の人達は大食いなのだ。だから幕府の考えていた食事量では全然、足りなかったのだ。何事も現地へ行ってみなければ分からない事というのがあるのだな」
安吾氏は世代的には戦前の作家に入りますので、戦前の一般家庭の食卓事情の常識は私達とは違い、一人あたり米五合という時代を生きた人であったはずです。その安吾氏が驚くほどですから、当時の長崎チャンポンの量の物凄さがうかがえます。
安吾氏の体験は、地方では江戸よりも更に大量の食事が取られていたらしいことの一例として理解できます。そういった地方から上京してきた丁稚奉公の小僧さんなどが江戸に来て「美味い白米」を味わったら、もう止まらないでしょう。
「一俵の米があっという間になくなる」
これは江戸時代に店を経営する人達にとって切迫した大問題であったのです。
おわりに
現代とは違い、電車も自動車も電気器具もない時代においては、すべてが人力でした。それは作業をする人が多くのカロリーを消費することを意味します。そして食卓のバラエティがとても少なく、カロリーを大量に補給するには米をたくさん食べる必要があったのです。当時、こうした量を食べても太っている人は稀でした。むしろ筋骨隆々という人達がほとんどだったそうです。「一日に四合の玄米」というのは、飽食の時代と呼ばれる現代から見ると、一見妙に見えますが、人力で毎日重労働をしている環境においては、普通のことなのかもしれません。
【主な参考文献】
- 坂口安吾 『安吾の新日本地理(第6回)長崎ちゃんぽん-九州』 青空文庫
- 永瀬清子『文芸読本 宮澤賢治』(河出書房新社)
- 杉浦日向子『一日江戸人』(新潮文庫)
- 江戸東京博物館HP 江戸時代の男女の平均身長はどのくらいか
- 福井の米屋 【豆知識】お米の単位にはどんなものがある?



コメント欄