【マヨラー必見】マヨネーズが消えた戦時下、日本人が生み出した「幻の代替品」とは?
- 2025/08/27
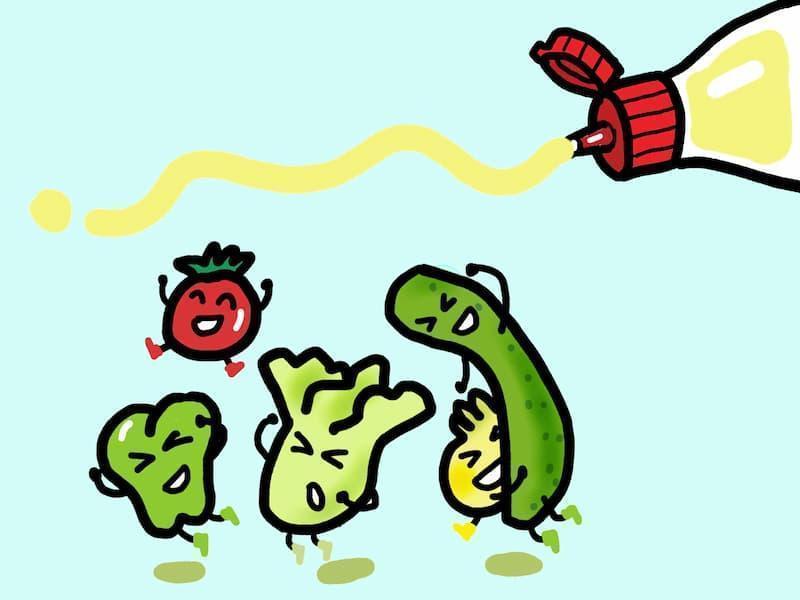
- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
お好み焼きにマヨネーズ、冷麺にマヨネーズ、ピザにマヨネーズ、鶏の唐揚げにマヨネーズ、パスタや生野菜はもちろん白飯にマヨネーズぶっかけの究極のずぼら飯まで。一億総マヨラーと化した日本列島に、マヨネーズ何時ごろやって来たのでしょうか?
マヨネーズ誕生
「18世紀半ばフランスのリシュリュー公爵が、スペイン領の地中海メノルカ島マオンと言う港町で、オリーブ油と卵黄とレモン汁を混ぜたソースを肉料理にかけて食べた。気に入った公爵はパリに持ち帰り、以後“マオンのソース”と呼ばれた」
これがマヨネーズ誕生の定説です。
マヨネーズはウスターソースやカレー粉と共に明治時代に日本に紹介されたようですが、初期のころは“マイナイソース”と呼ばれ、ごく一部の上流階級が上野精養軒などで味わうものでした。「ご家庭で作れるマイナイソース」のレシピが載った料理本も上流階級向けのものでした。そんな高級調味料マヨネーズが現在のように広く愛用されるようになったのは、やはり”あの会社”の存在が大きいのです。
大正元年(1912)缶詰会社若狭商店に努めていた中島菫一郎(とういちろう)青年は、農商務省の海外実業実習生に応募し、アメリカへ渡りました。当時から日常的にマヨネーズで和えた野菜サラダを食べていたアメリカ人たち。中島は美味しく栄養価も高い調味料と注目します。
「帰国したら日本でも作ろう」
彼はそう考えました。
きっかけは関東大震災
大正12年(1923)9月1日、関東大震災が日本を襲います。その復興の過程で衣食住の洋風化が進み、これなら一般家庭にもマヨネーズが受け入れられると思った中島は、大正14年に商品名「キューピーマヨネーズ」として製造・販売に踏み切ります。これまでも精養軒の主人が料理本でレシピを紹介したり、東伏見宮妃殿下が日本女子大家政学科の学生たちに“蒸した小鯛の冷製メヨネエズソオスかけ”を教えたりしています。他にも板垣退助伯爵夫人主催の料理講習会でのマイナイソースや、小説『食道楽』の著者・村井弦斎の夫人のレシピなども残っています。しかし、一般家庭向けに売り出したのは中島のキューピーマヨネーズが最初なのです。
マヨネーズの味わいは日本人の口に合ったようで一般家庭にも広まって行き、昭和16年(1941)の出荷量は10万箱500トンにも達しました。しかし日中戦争が始まり、卵も油も手に入りにくくなると、「よい原料が入手できない」として会社は製造を一旦中止します。製造が再開されたのは戦後3年の昭和23年(1948)でした。
見よう見まねのマヨネーズ
戦中戦後の物資のない時代、醤油や味噌でさえ不足していたのですから、卵や油を大量に使う工場製マヨネーズはおいそれと生産できません。それでもマヨネーズの味が恋しい人々は、何とか手作りしようと工夫を凝らします。満蒙開拓団女子訓練所が教えるマヨネーズ
材料:卵黄身1個・大豆油90g・酢25cc内外・塩10g内外・胡椒少々
調理法:卵黄身を底広の器に取り大豆油を少しずつ入れてよくかき回す。酢を三分の一入れ油を入れ手を休めることなくよくかき回す。とろりとすれば残りの酢と塩・胡椒を入れる。
上記は日本陸軍糧秣廠の外郭団体である糧友会の月刊誌『糧友』(昭和14年(1939))4月号記載記事です。若い女性が極寒の地満州開拓地に渡っても、食べて行けるような技術を身に着ける一助にと書かれたものです。
ここではマヨネーズは“酢油ソース”と呼ばれており、白菜や馬鈴薯もこの酢油ソースをかければ美味しく頂けると書いてあります。開拓団のような厳しい環境の中でも、マヨネーズはかつての贅沢品ではなく、普通の調味料として扱われていました。
満蒙開拓団青少年義勇軍訓練所が出版した『日本農村と栄養』(昭和19年(1944))でも作り方が書かれており、そこでは「酢と油が分離した時の対処法」や「長期保存の仕方」も説明しています。
陸軍式マヨネーズ
材料:卵黄1個・西洋酢大匙半杯・サラダ油100ml・食塩・胡椒・砂糖・味の素各少々
調理法:丼或いは深皿に卵黄を入れ、食塩・胡椒・砂糖を入れて良くかき混ぜる。サラダ油を少しずつ流し入れ硬くなり過ぎれば酢を入れ、これを交互に繰り返し混和する。
これは陸軍の兵士向けに書かれた調理テキスト『軍隊調理法』(昭和12年(1937)糧友会編)に載っている代用マヨネーズの作り方です。軍隊でもこのころすでにマヨネーズは味噌・醤油と同じように必須の調味料となっていたようです。
戦後の代用マヨネーズ
マヨネーズは卵黄と酢と塩に植物性油脂を分離しないように混ぜて“乳化”させ、とろりとさせたソースです。この乳化の状態を安定して保てることがマヨネーズには必須ですが、これが一般家庭では難しく、マヨネーズは最初から家庭で作るものではなく既製品を買って味わうものでした。しかし戦後すぐには工場も動いていません。家庭人も考えました。
「とろりとすれば良いんでしょ、とろりとすれば」
そして様々な代用マヨネーズが登場します。
大豆粉マヨネーズ
鍋に大豆粉と水を入れ火にかけとろみがつけば塩と甘味料で味をつける。冷めてから胡椒・西洋辛子・酢を加える。油が手に入れば大豆粉を油で炒めてから作る。
国立栄養研究所と国民栄養振興会が編集した『栄養食の作り方―配給食品の栄養と調理』(杜陵書院 昭和23年(1948))記載です。作ってみると大豆粉のざらつきが最後まで残るものの、大豆のコクもあり最初の水を出汁に変えると結構美味しいそうです。この大豆粉ベースのマヨネーズは卵アレルギー対策として、現在では豆乳マヨネーズとして製品化されています。
小麦粉マヨネーズ
鍋に小麦粉と水・牛乳を入れ火にかけ3分間煮る。冷ましてから溶き辛子・酢・塩・胡椒で味を調える。
『婦人生活7月号』(婦人生活社 昭和24年(1949))記載のもので、同様のものに片栗粉マヨネーズがあります。どちらもともかくとろみをつけてしまえとして考えられたものです。
馬鈴薯マヨネーズ
馬鈴薯を柔らかく茹でて潰す。油を加え酢を垂らしながら掻きまわす。滑らかになったところで塩・胡椒で味を調える。
『家庭料理』(主婦之友社 昭和23年(1948))記載。どうもマッシュポテトが出来上がるような気がするのですが、レシピ自らも「変わりマヨネーズ」と名乗っています。
他にも粉ミルクマヨネーズや味噌マヨネーズ・失敗しないマヨネーズ・バターマヨネーズなどが名乗りを上げています。
おわりに
現在ではJAS規格でマヨネーズとは「半固体状ドレッシングのうち卵黄又は全卵を使用し・・・」と決まっていますが、1950年公布のJAS法など無かったころ、何とかしてマヨネーズらしき物を作りたい味わいたい。そこまでして求めるほどマヨネーズは日本人の味覚にピッタリ合致したようです。【主な参考文献】
- 福場博保(編)、小林 彰夫 (編)『調味料・香辛料の事典』(朝倉書店、2009年)
- 八百啓介(編)『外来食文化と日本人』(弦書房、2020年)
- 魚柄仁之助『国民食の履歴書』(青弓社、2020年)


コメント欄