関ヶ原合戦、西軍の組織構造と石田三成の立場とは?…五大老・五奉行制の視点から
- 2023/10/24

関ヶ原合戦といえば、一般的に「徳川家康 vs 石田三成」という対立構造を思い浮かべる方が大半だと思われます。しかし、近年の研究では関ヶ原合戦における定説が見直される傾向にあります。その一つが石田三成の立場に関することです。
これまで三成は西軍の中心人物として認識されていましたが、三成以外にも多くの武将が西軍の中心人物として西軍の組織や運用に関わっていたことが明らかになってきています。
そこで本記事では、最新の研究を基に、改めて関ヶ原合戦における西軍の組織構造と石田三成の立場について考察してみたいと思います。
これまで三成は西軍の中心人物として認識されていましたが、三成以外にも多くの武将が西軍の中心人物として西軍の組織や運用に関わっていたことが明らかになってきています。
そこで本記事では、最新の研究を基に、改めて関ヶ原合戦における西軍の組織構造と石田三成の立場について考察してみたいと思います。
豊臣政権の後継者問題
第2代関白・豊臣秀次が切腹
天正19年(1591)8月、豊臣秀吉は唯一の実子である鶴松を亡くしました。子宝に恵まれなかった秀吉は、実子の誕生を諦め、甥の秀次を後継に指名、同年12月28日に関白職を譲ります。実権は引き続き秀吉が握っているとはいえ、ここに豊臣政権は秀次が継承することになり、それが内外に示されたのです。しかし、文禄2年(1593)には実子の秀頼が誕生します。これは後継者問題が再燃したことを意味しており、秀次の未来に暗雲が立ち込めます。とはいえ、秀吉は秀次の娘と秀頼の縁組を決めたり、日本を5つにわけて、そのうちの4つを秀次に、1つを秀頼のものとする案を提示したりと、秀頼の将来を考えつつも、秀次も立てる路線を模索していました。
しかし文禄5年(1595)7月、秀次は謀反の疑いをかけられ、高野山に出奔してしまいます。そこで無実を証明するため、彼は自害に及びました。
秀次の処遇をめぐっては、近年、秀吉は秀次を切腹にはさせず、高野山追放で済ますつもりであったのではないか、という見解もあります。もし秀次が生きていれば、後年の五大老・五奉行の設置は無かったかもしれません。
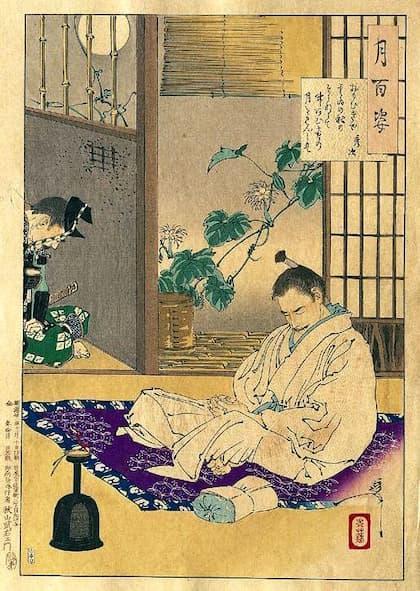
後継者秀頼と五大老・五奉行の設置
いずれにせよ、秀次の死により、秀吉の後継者は秀頼となりました。しかし、当時の秀頼は幼少であり、そして秀吉は高齢の身でした。秀頼の将来を案じた秀吉は秀頼の立場を固めるため、数え5歳で元服させ、官位の昇進を行いました。慶長3年(1598)6月、以前より健康を害していた秀吉は重篤な状態に陥ります。後継の秀頼がまだ幼少だったという点も相まって、豊臣政権は極めて不安定な状態になったといえます。死期を悟った秀吉は苦肉の策として秀頼が成人するまでの間、有力な大名(五大老)を政権中枢に参画させ、実務を担当してきた側近(五奉行)と共同で政権運営にあたる体制を整えました。
いわゆる「五大老・五奉行」の設置です。以下のメンバーが五大老・五奉行です。
- 五大老:徳川家康・前田利家・宇喜多秀家・上杉景勝・毛利輝元
- 五奉行:前田玄以・浅野長政・増田長盛・石田三成・長束正家
なお、この「五大老」「五奉行」という名称は江戸時代につけられたものと考えられており、当時の史料では様々な呼び方がされていたことが明らかになっています(以下本記事では便宜上「五大老」「五奉行」を使用します)。
秀吉は自身の死後、今まで実務を担当していた石田三成等の五奉行に引き続き政治運営を任せたうえで、五大老には五奉行の政治運営に支障が生じないように補佐役としての役割を求めました。このような体制で秀頼が成人するまでの間、政権を運営させようと秀吉は考えていたようです。
そして8月18日、秀吉は62歳の生涯を終えました。
奉行三成の失脚と大老前田家・上杉家の動向
秀吉死後も、五大老・五奉行制によって秀頼が成人するまでの政治運営を乗り切る方針でしたが、すでに豊臣政権において内部対立が生じていました。慶長4年(1599)閏3月、調整役を担っていた五大老の前田利家が亡くなったことを契機に政権内部の対立が表面化、特に有名なのは加藤清正・福島正則・浅野幸長ら7将が石田三成を襲撃した事件でしょう。この事件によって三成は佐和山城に引退が決まり、豊臣政権の中枢から外れることになったのです。
この後、伏見城にいた家康は秀頼のいる大坂城に入城し、豊臣政権の執政役として家康が政治運営を主導するようになっていきます。そのような中、家康は五大老の前田利長(利家の嫡男。利家死後に五大老に列する)と上杉景勝に謀反の嫌疑をかけました。利長は母の芳春院を人質に差し出し、徳川氏に恭順しましたが、景勝は家康の上洛要請を拒否したため、家康は上杉氏征伐(会津征討)の実施を決定します。
慶長5年(1600)6月16日、家康は5万5800人の軍勢を引き連れ、会津に向けて大坂城を出陣。これは西軍が挙兵するおよそ1ヶ月前の出来事でした。
※参考: 関ヶ原合戦(本戦)までの大まかな流れ(各前哨戦は省略)
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 慶長4年(1599) 閏3月 | 石田三成襲撃事件 |
| 9月7日 | 家康暗殺計画が発覚 |
| 慶長5年(1600) 6~7月 | 会津征伐(上杉景勝征伐) |
| 7月11日 | 石田三成が挙兵 |
| 7月 | 小山評定(下野国小山にて) |
| 9月15日 | 関ヶ原の戦い(本戦) |
西軍挙兵と石田三成
7月19日、江戸に到着していた家康に、11日に三成が挙兵したとする情報が舞い込んできました。ここでは三成の挙兵について取り上げたいと思いますが、実は家康が会津に出陣した時期から挙兵(7月11日)までの石田三成の動向についてはよくわかっていません。しかし、6月20日付けで三成が直江兼続(上杉景勝重臣)に宛てた書状には、毛利輝元と宇喜多秀家を「無二ノ味方」と位置付けており、この時期から三成・輝元・秀家の間で挙兵に向けて準備が進行していたとみられます。
このうち毛利輝元については、五奉行の前田玄以・増田長盛・長束正家の連名による7月12日付けの書状で、大坂城入城の要請がありました。この書状が広島に届けられると、輝元は15日に1万の軍勢を率いて出陣して海路を進み、翌16日には大坂城に入城しています。この迅速な行動から輝元は事前に出陣の準備を進めていたことがわかります。
そして、大坂城入城の翌7月17日、前田玄以・増田長盛・長束正家の連名で秀吉の遺命に背いたとして、家康弾劾状を諸大名に向けて発し、各地の大名に反家康方に味方するように要請しました。また、同日に輝元と秀家は、同じく大老の前田利長に書状を送り、味方に付くように勧誘しています。
ここから、西軍への勧誘工作は三奉行(前田玄以・増田長盛・長束正家)を中心に行われ、大老の前田家については、同じ大老の毛利輝元・宇喜多秀家が勧誘工作をしており、三奉行と二大老の間で役割分担があったとみられています。
以上の流れを整理すると、三成は少なくとも6月頃までには毛利輝元・宇喜多秀家と結んでおり、反家康の挙兵準備を進めていました。そして、大坂にいた前田玄以・増田長盛・長束正家も、挙兵準備に加担しており、諸大名に向けての家康弾劾状の作成・発布や西軍への勧誘工作にあたっていました。
つまり、西軍組織の中核は、三成だけでなく、三成を含めた2人の大老(毛利輝元・宇喜多秀家)と4人の奉行(石田三成・前田玄以・増田長盛・長束正家)と、複数で構成・運用されていたということです。そして、西軍は会津にいるもう1人の大老・上杉景勝と挟撃するかたちで家康との戦いに臨むつもりだったのです。
なお、五奉行の1人、浅野長政についてはすでに一線を退いており、関ヶ原合戦では息子の幸長とともに家康方に付いています。
西軍の総大将毛利輝元の立場
最後に西軍の総大将について取り上げたいと思います。一般的に総大将は毛利輝元ですが、それは形式上のもので、実態は石田三成が指揮を取っていたとされています。しかし近年の研究では、大坂城に入った輝元の名で多くの軍令や書状が発給されていたことから、実際に輝元が総大将として機能していたのではないか、と指摘する見解があります。
さらに、関ヶ原合戦(9月15日)直後の9月24日、加藤清正が鍋島直茂に戦況を伝えた書状には
「天下之様子、関ヶ原表之合戦、輝元方敗軍ニ付」
と記されており、ここから清正は西軍の総大将は輝元であると認識していたことが確認できます。
おわりに
ここまで、西軍の中心は石田三成のみでなく、2大老(毛利輝元・宇喜多秀家)・4奉行(石田三成・前田玄以・増田長盛・長束正家)を中心に構成されていたことを述べてきました(後に大老上杉景勝と合流予定)。従来は「徳川家康 vs 石田三成」の対立視点で捉えられることが多かった関ヶ原合戦ですが、このようにみると、秀吉が亡くなる直前、苦肉の策として設置した五大老・五奉行の枠組みに基づき、西軍の中枢は構成されていたことが窺えるかと思います。
五大老・五奉行の制度は、秀吉が苦肉の策として設置した割には、関ヶ原合戦まである程度は機能していたといえるかもしれません。
【主な参考文献】
- 谷徹也編『石田三成』(戎光祥出版、2018年)
- 柴裕之編『図説豊臣秀吉』(戎光祥出版、2022年)
- 小川雄・柴裕之編『図説徳川家康と家臣団』(戎光祥出版、2022年)
この記事を書いた人
大学・大学院で日本史を専攻。専門は日本中世史。主に政治史・公武関係について研究。現在は本業の傍らで歴史ライターとして活動中。
※旧ペンネームは yujirekishima
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。




コメント欄