明智光秀の鉄砲はプロ級…越前で磨かれた才能「朝倉義景家臣説」は本当か?
- 2025/09/01

明智光秀は前半生において、斎藤道三・義龍親子の争い(長良川の戦い、1556年)で居城・明智城を追われた後、越前の戦国大名・朝倉義景(1533~73)を頼って数年間仕えた、とされてきました。しかしこの説には確固たる根拠がなく、本当に義景の家臣だったのか、再考の余地があります。
ここでは、光秀の越前時代に関する既存の情報を整理し、その真偽について考えてみます。
ここでは、光秀の越前時代に関する既存の情報を整理し、その真偽について考えてみます。
朝倉義景に仕えた記録
そもそも明智光秀が越前の朝倉義景に仕えていたという証拠の出所は、悪名高い『明智軍記』です。この書物は創作性が強く、事実をありのままに記したとは言い難い軍記物であり、歴史を知る一級史料とはみなされていません。しかし、他にめぼしい史料がないため、この書物を中心に得られる情報を見てみましょう。『明智軍記』によれば、永禄6年(1563)ごろ、義景に仕えていた光秀は鉄砲の名人だったようです。この年、義景の命で鉄砲の腕前を披露する機会があり、光秀は大勢の人が見物する中で100発撃ち、黒星に66、的の角に32を当てたといい、9割以上を的に当てる才能を持っていたということのようです。
この才能は、加賀一向一揆との戦いで発揮され、光秀は鉄砲隊を50数名率いて戦功を挙げ、義景から感状と馬を賜ったと記されています。
また、光秀は明智城から出て諸国を流浪していた時代があり、そのころ各地の情勢や軍法を見聞きしていたことから、軍略に長けた人物であったとしています。ただし、わずか2年で全国を旅したという記述は信憑性が低く、事実ではないという説が有力です。
このように武士としての能力を認められていた光秀ですが、永禄8年(1565)ごろから義景に疎まれるようになります。鞍谷刑部・大輔嗣知(くらたにぎょうぶのたいふつぐとも)が義景に讒言します。
大輔嗣知:「光秀は才能や知恵はあるが気質が悪く、やがては謀反を起こす可能性もある」
義景はこれを信じて光秀を疎んじるようになり、越前で居心地が悪くなった光秀がやがて織田信長に仕えるようになったとしています。そこに付け加えると、明智城を攻めた張本人である斎藤竜興(義龍の子)が美濃攻防戦で信長に敗れ、朝倉義景を頼って越前に来たことも、光秀が朝倉の家臣をやめるきっかけだったとか。
義景・光秀・将軍義昭・信長の関係
光秀が義景に仕えていたかどうかは定かではありませんが、将軍足利義昭を介して両者が接触していたのは事実と考えられています。『明智軍記』や『綿考輯録(細川家記)』によると、朝倉義景は光秀に五百貫の土地を与えたとされています。義景は13代将軍・足利義輝が永禄の変(1565)で暗殺された後、その弟である義昭を越前の一乗谷に迎え入れ、側近の細川藤孝らとも交流を深めました。しかし、義景は義昭が望む上洛戦にまったく乗り気ではなく、業を煮やした義昭は、光秀の仲介で織田信長を頼ることになります。こうして信長の助力を得た義昭は、ついに上洛を果たしました。
この出来事をきっかけに、光秀は信長の家臣になったとされています。一方、義景は光秀に裏切られたと感じ、 浅井長政と共に信長と敵対する道を選びました。元亀元年(1570)の姉川の戦いをはじめ、信長に徹底抗戦しますが、天正元年(1573)の一乗谷城の戦いで大敗。最期は一族にまで裏切られ、自害に追い込まれました。
朝倉家臣説の根拠
ほとんどの明智光秀に関する研究書や書籍は、『明智軍記』などの記録をもとに、光秀が朝倉義景に仕えていた説を有力視しています。明智研究の金字塔とされる、高柳光寿氏の著書『明智光秀』(吉川弘文館)も、この説を支える一冊です。この本は、光秀が天下を狙っていたという「野望説」を打ち立てたことで知られています。この書物が発行されたのは昭和33年ですが、それでもいまだ明智光秀や本能寺の変に関しては根強く支持されています。
しかし、その高柳氏自身も『明智光秀』の中で、以下のように述べています。
「ところで光秀が越前へ行って朝倉義景に仕えていたということであるが、このことについては確証がないが、或いはそれは事実であったかも知れないと思わないではない。」
この記述の根拠は、結局のところ『明智軍記』、そしてそれから引用されたと考えられる『細川家記』によるもののため、「確証がない」とされています。高柳氏は、これらの史料は信用できないとしながらも、なぜ朝倉家臣説を信じているのでしょうか?
その理由は、高柳氏が『古案』という古文書集の記事を挙げ、家臣説を補強しているからです。
光秀が服部七兵衛尉に宛てた文には、「竹」という人物に百石の知行を与えると記されています。高柳氏によると、この「竹」という人物は、義景の近臣だった可能性があり、また百石もの知行を与えられている関係から、「竹」と光秀は非常に親しかったことが推測されるとのこと。このことから高柳氏は、光秀がかつて義景に仕えていたという説を展開しているのです。
ただ、この論証は、まるで「友達の友達は友達か?」というように、回りくどく、これだけで「やはり仕えていた!」と言い切るには説得力に欠けているように筆者は思えますね。
明智憲三郎氏は否定
多くの研究が朝倉家臣説を支持している一方で、家臣ではなかったとする説も。明智憲三郎氏は、著書『本能寺の変 431年目の真実』(文芸社文庫)で、光秀が朝倉家の家臣であったという説を否定しています。その根拠として、家臣説を裏付ける史料が『明智軍記』や『細川家記』といった信憑性の低いものに限られること、また、高柳光寿氏自身も曖昧な表現にとどまり、断言できていないことを挙げています。
では、光秀がこの時期に誰に仕えていたのか。明智氏は、光秀が細川藤孝の部下(中間)として、幕臣の身分にあったと主張しています。
また、光秀が朝倉家に仕えていたと断言はしないまでも、元々幕府側の人間であり、将軍 足利義昭が越前に滞在した際に義景との付き合いが始まり、そこで家臣になったという見方もあります。
おわりに
これまで見てきたように、有力説とされてきた光秀の朝倉家臣説は、その根拠が実は曖昧であることがわかります。改めて文献を見直すと、家臣説を提唱した高柳光寿氏の論ですら、決して断定的なものではなく、「仕えていたと考えることもできるかもしれない」という、あくまで推論の域にとどまっている印象を受けます。
結局のところ、「有力説」とされていても、確実なことは何も分かっていません。「○○という史料によれば、そうだったらしい」としか言えないのが現状です。
信長の家臣になる前の光秀については史料が極めて少なく、その前半生はまさに謎に包まれています。結論として言えるのは、光秀が朝倉義景の家臣であったかどうかは依然として不明であるということ。世間で「有力説」とされているからといって、鵜呑みにはできないのです。明智光秀の生涯には、いまだ多くの研究の余地が残されていると言えるでしょう。
【主な参考文献】
- 高柳光寿『人物叢書 明智光秀』(吉川弘文館、1986年)
- 二木謙一編『明智光秀のすべて』(新人物往来社、1994年)
- 谷口克広『検証 本能寺の変』(吉川弘文館、2007年)
- 新人物往来社『明智光秀 野望!本能寺の変』(新人物文庫、2009年)
- 明智憲三郎『本能寺の変 431年目の真実』(文芸社文庫、2013年)
- 歴史読本編集部『ここまでわかった!明智光秀の謎』(歴史読本編集部、2014年)
この記事を書いた人
大学院で日本古典文学を専門に研究した経歴をもつ、中国地方出身のフリーライター。
卒業後は日本文化や歴史の専門知識を生かし、 当サイトでの寄稿記事のほか、歴史に関する書籍の執筆などにも携わっている。
当サイトでは出身地のアドバンテージを活かし、主に毛利元就など中国エリアで活躍していた戦国武将たちを ...
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。



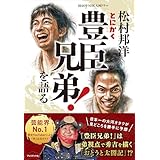
コメント欄