松本秀持 蝦夷地(北海道)の可能性を初めて見出した勘定奉行
- 2025/02/04
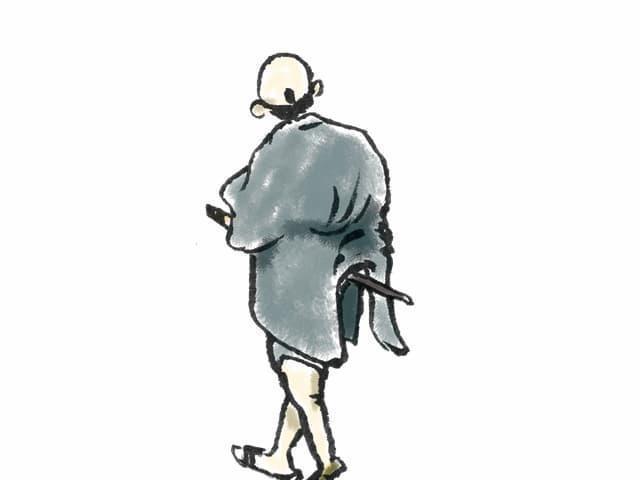
- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
田沼意次の経済政策の中でも下総国(千葉県北部)の印旛沼・手賀沼の干拓事業、そして蝦夷(北海道)の開拓はよく知られていますが、これらの事業を実際に行ったのが、2025年大河「べらぼう」に登場予定の人物、松本秀持(まつもと ひでもち、1730~1797)です。
松本はもともとは天守番という低い身分でしたが、田沼意次に見いだされて勘定奉行にまで出世した人物です。彼が担当した事業の中でも北海道開拓は特筆されるもので、江戸幕府が始めて北海道に直接調査を行うことに成功し、北海道の可能性を見出しました。
残念ながら田沼意次の失脚とともに担当役から外され、蝦夷地開拓は実際には行われませんでしたが、彼の調査は後々の政策に大きな影響を与え、明治政府が北海道開拓に乗り出すのです。
松本はもともとは天守番という低い身分でしたが、田沼意次に見いだされて勘定奉行にまで出世した人物です。彼が担当した事業の中でも北海道開拓は特筆されるもので、江戸幕府が始めて北海道に直接調査を行うことに成功し、北海道の可能性を見出しました。
残念ながら田沼意次の失脚とともに担当役から外され、蝦夷地開拓は実際には行われませんでしたが、彼の調査は後々の政策に大きな影響を与え、明治政府が北海道開拓に乗り出すのです。
蝦夷地の情報
当時、蝦夷地は松前藩(まつまえはん。現在の北海道松前郡松前町に居所を置いた藩)が全権を握っており、徳川幕府といえども簡単に蝦夷地に足を踏み入れることはできませんでした。というのも、蝦夷地は江戸から遠く、松前藩からも何の情報もなく、ただ海産物が送られてくるだけであり、松前藩が支配する独立国家のような雰囲気だったのです。もし蝦夷地になんらかの経済的メリットが判明していたら江戸幕府も早々に動いていたかもしれませんが…。
そんな時、天明3年(1783)に仙台藩の藩医だった工藤平助が江戸幕府に『赤蝦夷風説考』(あかえぞふうせつこう)という研究書を提出しました。工藤平助は松前藩藩士などから、北方でのロシア帝国進出の事実を知り、危機感を持って研究書を作成、提出したのです。
いくら日本が鎖国をしていようが、外国が武力進出してくる可能性はありますから、これは真剣に検討せざるを得ないものでした。松本秀持は特に危機感を募らせ、自ら田沼意次に蝦夷地探索の提言を行い、その許可を取ったのです。
松前藩との交渉
田沼意次の許可がおりたものの、松前藩は江戸から遠く離れていることを良いことに幕府の権威を素直には受け入れず、松本秀持の調査依頼も門前払いしました。松前藩は蝦夷地の先住民であるアイヌ民族から海産物を搾取しており、そういった事実が幕府に知られるのを嫌ったものと言われています。しかし、勘定組頭であり、蝦夷地に詳しい土山宗次郎からの情報などを元に、松本秀持は松前藩と交渉を重ねていきます。そしてなんとか調査隊の派遣を認めさせることができた結果、蝦夷地の地質が農業に極めて向いていることを発見します。松前藩は収入になる海産物の水揚げにアイヌの人達を集中させ、農業を禁止していたため、これが見逃されていたのです。
開発計画の立案
広大な蝦夷地を開拓することで多大な農産物が得られる点に気づいた松本秀持は、蝦夷地開発計画を立案します。何しろ広大な面積ですから相当数の人手が必要です。そこで目を付けたのが、江戸時代の身分制度で一番下に置かれていた穢多・非人を統括する弾左衛門(だんざえもん。頭領の名称)です。つまり、江戸で最下級の身分として虐げられている人達を集め、蝦夷地開拓を行おうという計画でした。
虐げられている人達の解放にもつながるため、弾左衛門も了承しましたが、蝦夷地開発計画が実行される寸前に田沼意次が失脚。それに伴って松本秀持もお役御免となってしまい、この計画は実現されませんでした。
もし実現していたら、とても早い段階で北海道の開拓が行なわれ、多くの人達が虐げられている状況も脱出できたかもしれません。誠に惜しい頓挫でした。
一説によると、田沼意次は蝦夷地開発を平賀源内に任せようとしていたそうですが、彼が誤って人を殺してしまったため、人選から外れたとのことです。もし平賀源内が蝦夷地開拓を担当、実施していたら随分と面白い歴史が残されたことを思うと残念です。
以降の徳川将軍、幕府の閣僚達は蝦夷地に興味を示さなかったため、蝦夷地の開発は明治時代に入ってからとなりました。工藤平助が心配していたロシア帝国進出はほとんど行われず、結果的に蝦夷地は日本の領土であり続けましたが、もしロシア帝国の進出がされれば、蝦夷地は侵略を受けていたかもしれません。それを考えると、ちょっと怖いものがありますね。
おわりに
松本秀持の蝦夷地調査は、明治政府になってから活かされ、北方侵略対策が取られることになったため、決して無駄な物ではなかったといえます。また、彼の計画が実行されていれば、松前藩によるアイヌ民族の搾取問題なども改善される可能性があったことを考えると、計画頓挫は実に無念ではあります。しかし、この一事をもってしても田沼意次の政策がいかに先進的な物であったかが伺えるのです。
何しろ、以降の徳川将軍や幕府の閣僚らは、やろうと思えばできたはずなのに、成功すれば明らかに大きな経済改善につながったであろう「蝦夷地開拓」に全く興味を示さなかったのですから。もっとも幕末期に入ってしまうと、それどころではない事態になってしまうのは皆さんもご承知の通りですが…。
【主な参考文献】
- 上田正昭、西澤潤一(編)ほか『日本人名大辞典』(講談社、2001年)
- 賀川隆行『崩れゆく鎖国 日本の歴史11』(集英社、1992年)
- 浦本誉至史『江戸・東京の被差別部落の歴史 : 弾左衛門と被差別民衆』(明石書店、2003年)



コメント欄