「どうする家康」家康 VS 信玄 『三河物語』は三方ヶ原合戦をどのように描いたか?
- 2023/05/15

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
大河ドラマ「どうする家康」第18話「真・三方ヶ原合戦」。三方ヶ原合戦での徳川家康 と家臣の様子が描かれました。元亀3年(1572)12月22日、三方ヶ原(静岡県浜松市北区)において、武田信玄と徳川家康・織田信長が派遣した援軍が激突します。両軍はどのように戦をしたのでしょうか?
ここでは『三河物語』(江戸時代初期の旗本・大久保彦左衛門の著作)の記述に拠って、 三方ヶ原合戦の展開を見ていきましょう。同日、家康は武田軍が浜松から三里ばかりの距離まで迫ってきて、出陣します。ドラマや小説等においては、家康の居城・浜松城において、家康と重臣たちが、籠城するか、それとも武田軍と合戦するか、意見を戦わせるようなシーンがあるかと思いますが『三河物語』の文章を見ていくとそうではないことが分かります。
家康と重臣らは、城から打って出てから、武田軍と戦をするか否か、軍議をしているのです。「一合戦しよう」と主張する家康。しかし、重臣たちは、敵は大軍(3万)であること、味方は小勢(8千)であること、信玄が熟練の武者であることを理由にして、皆、主君に異を唱えます。が、家康は「戦は多勢無勢で結果は決まらない」として、家臣の見解を却下して、武田軍に攻め寄せるのでした。
武田方からは、小石が飛んできますが、家康軍はそれを相手にせず、攻撃を仕掛けます。「一陣二陣を打ち破る」家康軍。武田軍は新手の軍勢を差し向けてきますが、家康軍はそれをも打ち破り、信玄の本陣に殺到したと言いますので『三河物語』だけ見ていると、家康軍が勝利するのではと感じてしまいます。あくまで同書の記述からは、緒戦は家康軍が優勢だったということができるでしょう。が、家康軍の優勢は長くは続きません。
信玄の本陣からの軍勢がぶつかってくると、8千の家康軍は、押されていくのです。家康は小姓衆を討たせまいと、馬をあちらこちらに走らせ、味方を丸く固まらせて退却していったそうです。それでも、信長が援軍として派遣してくれた平手汎秀、徳川の家臣たち (鳥居忠広・本多忠真・夏目吉信ほか)の多くが討死していきます。
家康より早く城に戻った家臣が「上様(家康)は戦死されました」と触れ回ったので、総大将は討死かと思われましたが、家康は無事に帰城します。「家康様は死んだ」と言っていた家臣らは気まずかったのでしょう。あちこちに、逃げ隠れたという「笑い話」もあります。



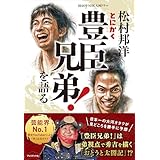
コメント欄