「土田御前」信長を憎む毒親として描かれる母親像は本当に存在したのか?
- 2025/08/07
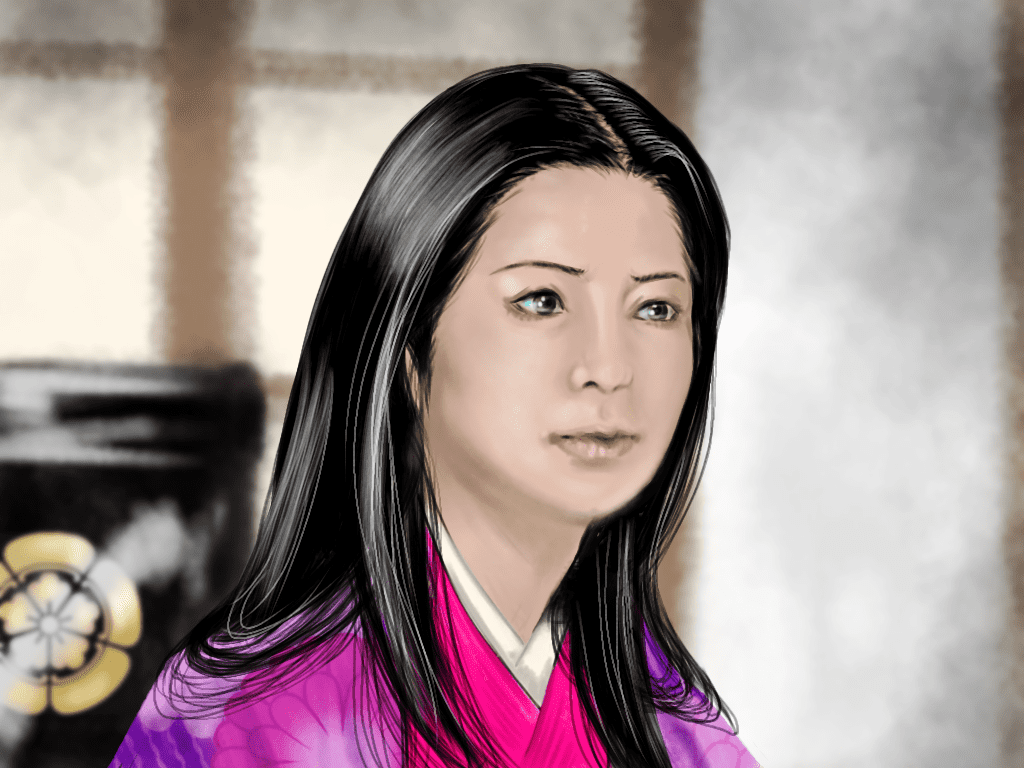
- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
織田信長の生母・土田御前(どたごぜん)については、私が好んで読む『信長公記』やルイス・フロイス『日本史』などにはほとんど記述がないので、あまり人物像をイメージできていなかった。そのような状況を一変させたのは、2002年放送の大河ドラマ『利家とまつ』であった。
反町隆史演じる織田信長が当時の宣教師が描いたとされる肖像画に若干似ていて、性格も尊大さをやや誇張させたものになっていたというのも面白かったのは確かである。しかし、もっと驚いたのは実の母との関係が極めて険悪だったという設定であった。信長が実の母親に向かって「儂を産んだ女」とのたまうあたり、織田家の闇を感じ取ったような気がしたものである。
このくだりが定説に基づいたものであったことは、のちに読んだ歴史書で知ったのだが、この土田御前像は本当に正しいのであろうか。その点を史料に基づいて紐解いてみたい。
反町隆史演じる織田信長が当時の宣教師が描いたとされる肖像画に若干似ていて、性格も尊大さをやや誇張させたものになっていたというのも面白かったのは確かである。しかし、もっと驚いたのは実の母との関係が極めて険悪だったという設定であった。信長が実の母親に向かって「儂を産んだ女」とのたまうあたり、織田家の闇を感じ取ったような気がしたものである。
このくだりが定説に基づいたものであったことは、のちに読んだ歴史書で知ったのだが、この土田御前像は本当に正しいのであろうか。その点を史料に基づいて紐解いてみたい。
二通りの読み方
土田御前は佐々木六角氏の末裔とされる土田政久の娘であるというのが一般的な説となっている。ところが、これには異説も複数存在する。例えば、『美濃国諸旧記』によれば、信長生母は六角高頼息女だというし、『干城録』(かんじょうろく)によれば、信秀正室・信長生母は小嶋信房息女とされている。
しかし、『美濃国諸旧記』にしろ『干城録』にしろ、江戸時代初期に成立した史料であるから一次史料とは言い難く、その内容を鵜呑みにするのは危険であろう。また、土田の読み方も未だ確定していない。美濃可児郡ゆかりの土田であれば「どた」であるが、尾張清州ゆかりの土田であれば「つちだ」だというのだが、どちらなのか定かではない。
信長を嫌っていたのは本当か
定説では、土田御前はうつけと評判であった嫡男信長を嫌い、弟の信行を可愛がっていたとされている。この定説は有名であり、小説やドラマのネタとしてかなり使われてきたという経緯から認知度は高い。
確かに信秀の死後、土田御前は信長のいる那古屋城ではなく、信行のいる末森城で暮らしているから、親子関係がギクシャクしていたのかもしれない。これは、信秀は信長を後継者に選んでいたが、既に織田家の重臣であった柴田勝家が信行派であり、信長の家督相続が取り消されて信行が当主になる可能性も十分あったからとは考えられないだろうか。それに、あの信長が可愛げのある子供であったわけはなく、扱いに困っていたという面もあるだろう。
信長と土田御前の関係を紐解く上で、私が気になっているのが信長の女性の好みである。信長は割と年上の女性が好みであったらしく、最愛の側室・吉乃も6歳年上であったという。心理学的に言うと、年上の女性を好む男性は、幼少期に母親から愛情をあまり受けなかった傾向があり、その結果、無意識に女性に母性を求めてしまうのだそうだ。この点を考慮すると、少なくとも幼少期の信長は、あまり土田御前に構われなかったのかもしれない。
一方で、『信長公記』によれば、信長が信行を謀殺しようと重病の振りをしたとき、土田御前は信行に対して次のように言ったとある。
「今までの関係はともかく、実の兄なのだからお見舞いに行くように」
これを踏まえると、信長は扱いにくい嫡男ではあるが、「嫌い」とか「憎い」という感情まで抱いているという所まではいっていないように思う。事実、信行は永禄元年(1558)に信長に誅殺されるのであるが、土田御前はその後、信長とともに暮らし、信長とお市の子供がまだ幼い折には彼らの面倒を見ていたという。
永禄3年(1560)桶狭間の合戦で今川義元を破った際には、純粋に我が子の成長ぶりを喜んだのではないだろうか。
信長死後の土田御前
桶狭間の合戦、足利義昭を奉じての上洛を経て、信長は天下統一事業に邁進するようになる。その事業がもう少しで完成という矢先、驚天動地の出来事が起こる。天正10年(1582)6月2日の本能寺の変である。これによって、土田御前は息子の信長と、嫡孫の信忠を相次いで失うこととなる。『氏郷記』によると、本能寺の変直後、蒲生賢秀(がもう かたひで)が安土城から日野城へ信長公御台君達などを避難させたという。この時点で土田御前は安土城にいたものと思われるので、ともに日野城へ向かった可能性もある。その後、信長次男である織田信雄の元に引き取られたという。
1587年頃の織田信雄家の家族構成や家臣、そしてその所領についてまとめた『織田信雄分限帳』には「大方殿」という女性の化粧料が「〇百四十貫文」と記載されている。化粧料とは、大名の母など身分の比較的高い女性に給付される生活費のことを指すのだが、この「大方殿」は土田御前であるとされている。
信雄の正室と思われる「御内様」は「五百貫文」と記載されていることを考えると、信雄の祖母である土田御前の化粧料が百四十貫文であるわけはなく、〇には何らかの数字が入っていたと思われる。そして、それはおそらく ”五” 以上の数字であろう。
天正12年(1584)、秀吉との対立で勃発した小牧長久手の戦いでは、信雄は徳川家康と同盟を組んで挙兵したにもかかわらず、状況が膠着すると秀吉と単独講和を結んでしまう。何とか生き延びた信雄であったが、天正18年(1590)の小田原征伐後に秀吉から「尾張→三河、遠江」への転封を命じられる。これは家康が「三河、遠江→関東」への転封があったため、対で行われたものであろう。しかし信雄はこの転封を拒否したことで秀吉の怒りを買い、改易となってしまうのである。
庇護者を失った土田御前は、やむなく伊勢国安濃津15万石の織田信包(のぶかね。信長の弟)のもとに身を寄せたという。
世は豊臣政権の天下統一によって平和となり、土田御前は平穏に余生を送ったものと思われる。そして彼女は文禄3年(1594)1月7日この地で逝去する。
あとがき
超有名武将である織田信長の生母でありながら、土田御前に関する記述のある史料は極めて少ない。これは正妻である濃姫も同様であるが、それにもまして少ないように思う。これら少ない史料を紐解いていく過程では、自然とその「行間」を読んでしまうことになる。もちろん、これは歴史学の世界ではご法度であろう。しかし、私は歴史コラム執筆者であるから、若干自由な立場でモノが言えるという利点がある。
あくまでその立場から言わせていただくと、どう考えても土田御前が信長をイジめるほど憎んでいたとまでは思えないのだ。もちろん人間であるから「ホントに可愛げのない子ね」と感じたり、諍いを起こしたりしたこともあったであろう。しかし、これと「憎む」感情の間には、割と大きな隔たりがあるように思えてならない。
これに関して、1つ気になることがある。土田御前は信長の尾張統一後から彼と暮らすことになったが、その際、信長の子供たちのみならず、浅井家滅亡後にお市の子である茶々や江などの世話をしていたということには先に触れた。
まずは、信長を憎むほど仲が悪ければ一緒に暮らすという選択はしなかったのではないか。もし仮に、信長は憎いが、何かの事情があって一緒に暮らさざるを得なかった場合、孫らの前で信長の評価を下げるような発言をして信長に対する信頼が棄損されてもおかしくはないはずである。
ところが、嫡男信忠などは終生に渡って父信長を畏敬していたように思える。他の子たちも信長との関係が悪かったという記述が史料には見られないのである。これは信長と土田御前はそれほど仲が悪くなかったという傍証にならないであろうか。
【参考文献】
- 柴裕之『織田氏一門』(岩田書院、2016年)
- 太田牛一『現代語訳 信長公記』(中経出版、2013年)
- 有光友学編『戦国期権力と地域社会』(吉川弘文館、1986年)
- 小和田哲男『織田家の人々』(河出書房新社、1991年)


コメント欄