【大阪府】芥川山城の歴史 大阪府下最大級の山城にして三好長慶の居城!
- 2020/04/27

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
「天下人」といえば一般に、「豊臣秀吉」や「徳川家康」、あるいは大きくその道筋をつけた「織田信長」などの名前を思い浮かべる人が多いでしょう。
戦国時代当時の「天下」とは京の都のことを指し、京洛と近畿地方に影響力をもった人物も「天下人」と呼ばれる資格がありました。近年、信長以前の最初期の天下人として周知されてきたのが「三好長慶」です。激しい下剋上の世でやがて三好氏の勢力も覆される運命にありますが、一時代を築いた長慶が居城とした山城の一つが「芥川山城」です。
今回はそんな、かつて近畿ににらみを利かせた芥川山城の歴史についてみてみましょう。
戦国時代当時の「天下」とは京の都のことを指し、京洛と近畿地方に影響力をもった人物も「天下人」と呼ばれる資格がありました。近年、信長以前の最初期の天下人として周知されてきたのが「三好長慶」です。激しい下剋上の世でやがて三好氏の勢力も覆される運命にありますが、一時代を築いた長慶が居城とした山城の一つが「芥川山城」です。
今回はそんな、かつて近畿ににらみを利かせた芥川山城の歴史についてみてみましょう。
芥川山城とは
「芥川山城」とは現在の大阪府高槻市、三好山にあった山城です。かつては単に「芥川城」と呼ばれていましたが、同市内にもう一つ同じ名前の城が存在したため、三好山所在の城を「芥川山城」として区別しています。三好山は標高約183m、そこに設けられた芥川山城は南北約400m、東西約500mに及び、大阪府下最大級の山城としても知られています。
最初にこの場所に城を築いたのは室町幕府管領となる「細川高国」で、永正12年(1515)頃のことと考えられています。
古記録によると、昼夜を通して工事が行われ、300~500人もの作業員が動員されたと伝わっています。城主には細川氏家臣で摂津の国人「能勢頼則」が就き、およそ三代にわたり能勢氏が世襲したと考えられています。
次に芥川山城に拠ったのは「細川晴元」で、一向一揆勢との戦闘で一時淡路国に退避していたものの、天文2年(1533)に摂津へと復帰・入城します。
晴元は天文6年(1537)に「右京大夫」に任官、室町幕府管領となりますが、京との往来において芥川山城を重用したとされています。
天文8年(1538)、晴元の家臣であった「三好長慶」が台頭し、主君を京から放逐します。芥川山城には長慶が一時入城したといいますが、晴元との和議によって退城。しかし両派の間での紛争は続き、天文16年(1547)、芥川山城は再び長慶の手にわたります。
長慶は一族の「芥川孫十郎」を城主に据えますが、謀反の嫌疑により、天文22年(1553)に包囲戦を展開、孫十郎に代わって長慶自身が城主となりました。
永禄3(1560)には長慶の子である「三好義興」が城主となり三好氏の拠点として継承されますが、永禄11年(1568)に「織田信長」の摂津攻めで落城。「和田惟政」が城主になります。
翌年、惟政は三好長慶の後継勢力である「三好三人衆」掃討の勲功により高槻城主を与えられ、芥川山城主には惟政家臣の「高山友照」が就任します。
しかし元亀2年(1571)、惟政は「中川清秀」「荒木村重」らに討たれ、子の「和田惟長」が高槻城主を継承します。その混乱に乗じる形で元亀4年(1573)、「高山友照・重友」父子が惟政から高槻城を奪取。その際に芥川山城は廃城となったと考えられています。
大阪府下の大規模山城である芥川山城は平成29年(2017)、日本城郭協会認定の「続日本100名城」に選定され、中世~戦国期城郭の姿を伝える史跡として周知されています。
あわせて読みたい
あわせて読みたい
本格的な建築物を備えた、「三好政権」の本拠地としての城
芥川山城は「三好政権の首都」とも例えられるように、政庁としての機能をもっていたことが知られています。一般的に戦国期の山城には簡易的な構造物しかない場合が多いですが、主郭から出土した礎石により、少なくとも床張りの4つ以上の部屋を備えた本格的な建物のあったことが判明しました。
また、古記録には弘治2年(1556)に「三好義興」と「松永久秀」の陣所で火事があったと伝わり、実際に火災の痕跡が発掘調査で確認されています。
この時に久秀は京都・醍醐寺に関係する所から建物を移築したと伝えられており、山城でありながら立派な居館のようなものを備えていたことが想像されます。
このように芥川山城は単純な要塞というに留まりませんが、要所ごとに設置された堀切や土塁が効果的に作用する堅固な要塞というのが本来の性格です。
土塁といえば通常は横方向に壁上に構築されるものですが、ここでは「竪土塁」という珍しいタイプのものも見ることができます。これは文字通り、曲輪や斜面に対して縦方向に設けられた土塁で、敵が斜面を迂回することを妨げるものとされています。
あわせて読みたい
おわりに
「最初の天下人」ともいわれる三好長慶をはじめ、多くの武将たちが重要な拠点と認識してきた芥川山城。要塞としての山城から、政庁としての城郭への過渡的な姿を示す好例といえるでしょう。補足:芥川山城の略年表
- 1515年(永正12年)頃 室町幕府管領「細川高国」により築城。「能勢頼則」が初代城主となり、以降1526年(大永6年)まで能勢氏が世襲
- 1533年(天文2年) 「細川晴元」が芥川山城に入城。晴元は1537年(天文6年)、管領に就任
- 1539年(天文8年) 「三好長慶」が細川晴元を京から放逐。芥川山城に入城するが和睦により退城
- 1546年(天文15年) 「細川氏綱」が芥川山城を奪取
- 1547年(天文16年) 「三好長慶」が芥川城を包囲、支配下に置く。三好一族の「芥川孫十郎」が城主に
- 1553年(天文22年) 謀反の疑いで芥川孫十郎を追放。三好長慶が城主となる
- 1560年(永禄3年) 長慶の子、「三好義興」が城主に
- 1568年(永禄11年) 「織田信長」の摂津攻めにより、芥川山城は落城。「和田惟政」が城主に
- 1569年(永禄12年) 惟政は三好三人衆撃退の功により高槻城主に。家臣の「高山友照」が芥川山城主となる
- 1573年(元亀4年) 「高山友照・重友」父子が戦乱に乗じて高槻城を奪取。芥川山城は廃城となる
- 2017年(平成29年) 日本城郭協会認定の「続日本100名城」に選定
あわせて読みたい
【参考文献】
- 『歴史群像シリーズ 戦国の山城』 全国山城サミット連絡協議会 編 2007 学習研究社
- 高槻市HP 芥川山城跡
- 高槻市HP 続日本100名城 芥川山城跡

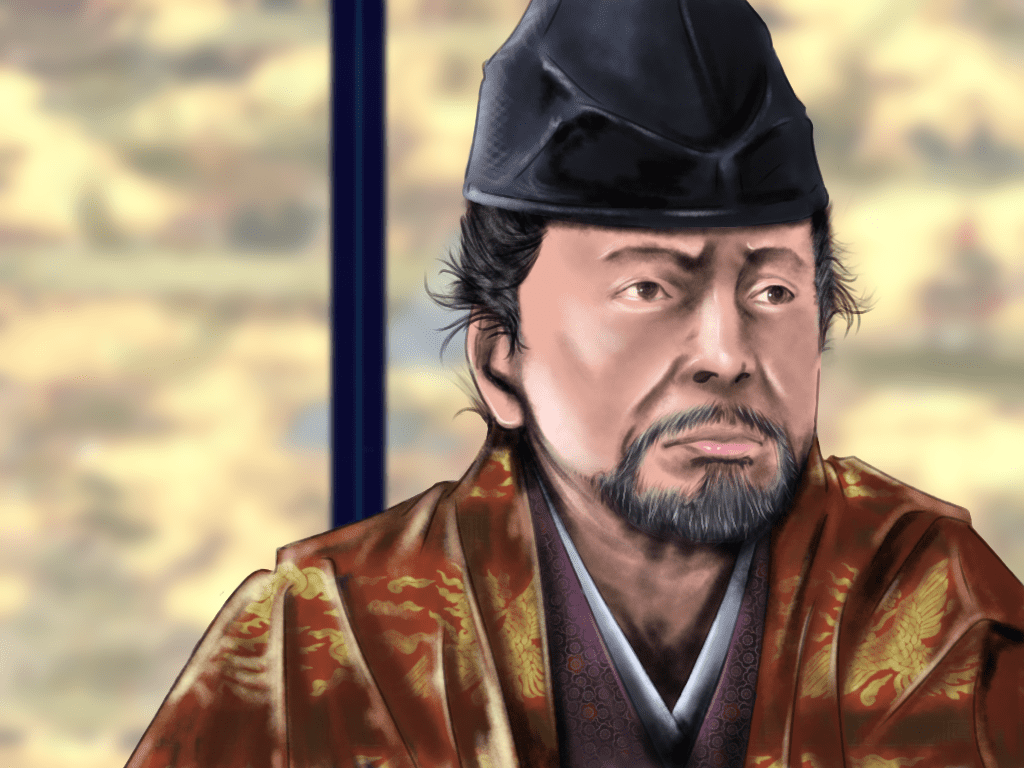

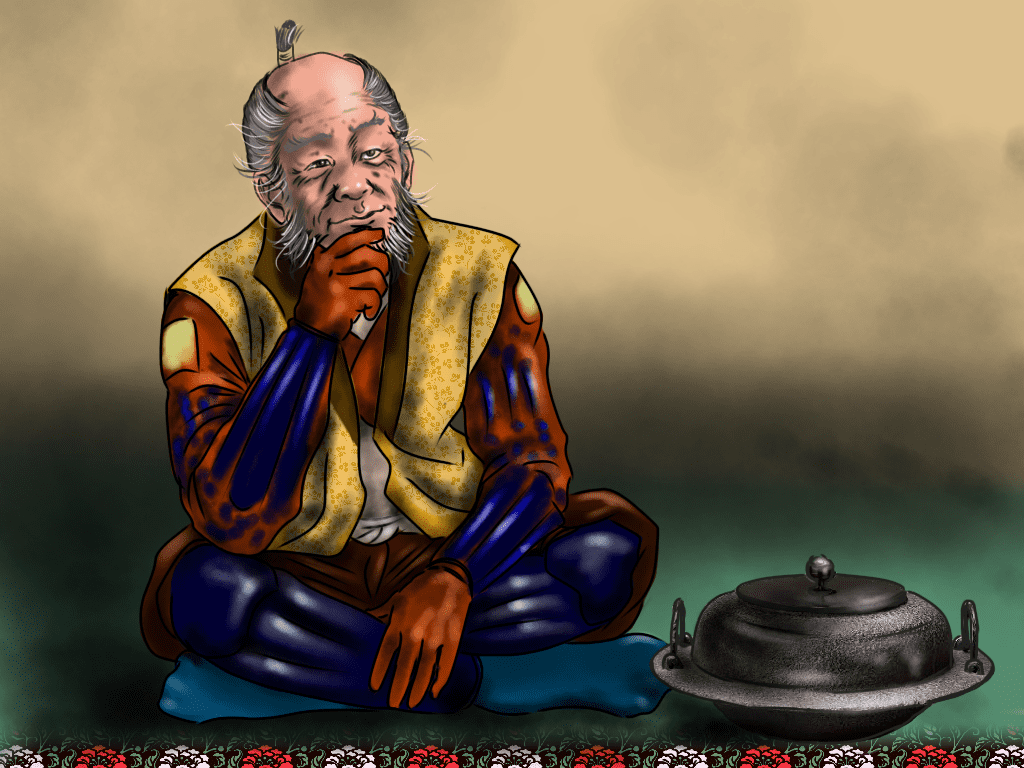




コメント欄