「小牧・長久手の戦い(1584年)」秀吉vs家康・信雄連合軍!両雄それぞれの強さが際立った大戦
- 2021/08/23
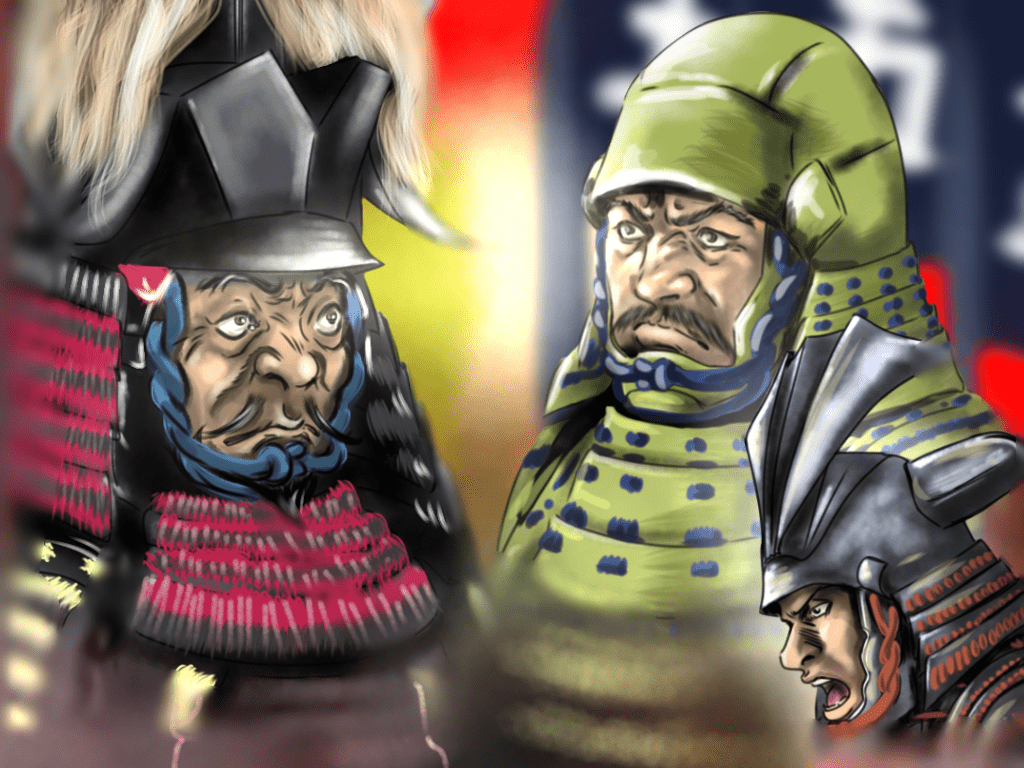
- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
本能寺の変で織田信長が倒れ、首謀者の明智光秀を討った羽柴秀吉が織田家中で絶大な影響力をもつに至ったのは周知のとおりです。しかし、柴田勝家を筆頭とした有力家臣のうちには、秀吉に従うことをよしとしない勢力も少なくありませんでした。
信長の嫡孫にあたる「三法師(のちの織田秀信)」を擁した秀吉は、天正11年(1583)に賤ヶ岳の戦いで柴田勝家を破り、名実ともに信長旧臣の筆頭格の座におさまりました。しかしそれでもなお、反秀吉の火種は消えることなくくすぶっていたのです。
今回はそんな秀吉 vs 反秀吉の戦のうち、天正12年(1584)に展開された 小牧・長久手の戦い にスポットライトを当ててみます。この合戦は一か所のみではなく、各地で連動して勃発した一連の戦闘を指しているため、「天正十二年の東海戦役」などの別名でも知られています。
天下人への梯子に手をかけた秀吉と、それを阻止しようとした勢力の戦いを概観してみることにしましょう。
信長の嫡孫にあたる「三法師(のちの織田秀信)」を擁した秀吉は、天正11年(1583)に賤ヶ岳の戦いで柴田勝家を破り、名実ともに信長旧臣の筆頭格の座におさまりました。しかしそれでもなお、反秀吉の火種は消えることなくくすぶっていたのです。
今回はそんな秀吉 vs 反秀吉の戦のうち、天正12年(1584)に展開された 小牧・長久手の戦い にスポットライトを当ててみます。この合戦は一か所のみではなく、各地で連動して勃発した一連の戦闘を指しているため、「天正十二年の東海戦役」などの別名でも知られています。
天下人への梯子に手をかけた秀吉と、それを阻止しようとした勢力の戦いを概観してみることにしましょう。
【目次】
合戦の背景
信長後継ポジションについての争い
天正10年(1582)6月に行なわれた清洲会議では、信長亡き後の領地再配分と織田家の後継問題が主な議題となりました。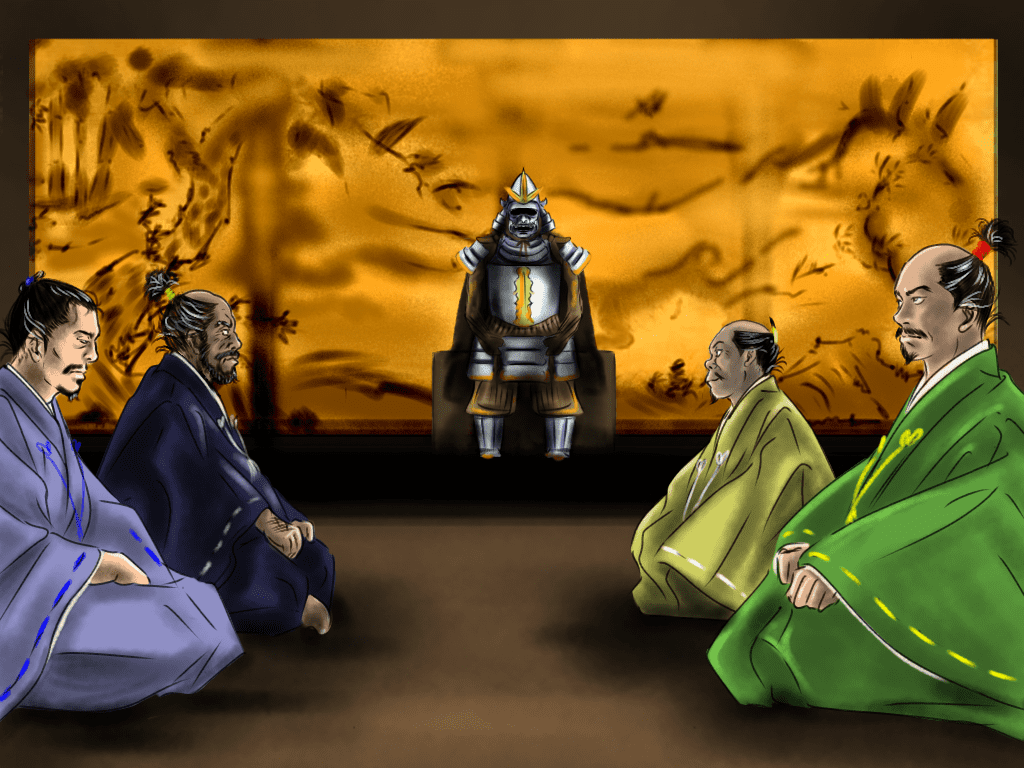
結論からいうと、織田家の後継者は信長の嫡孫である三法師(さんほうし。織田信忠の子)に決定。そして叔父にあたる「織田信雄」「織田信孝」らが後見する体制となりました。
信雄と信孝はそれぞれ、信長の次男、三男とされている人物です。信長と嫡男の信忠の両名が死亡した当時にあっては織田家の第一継承権者といえる立場にありました。信雄と信孝は、出生の順に諸説があるように、どちらが兄にあたるかの解釈もさまざまで、後継者問題ではどちらも自身の正当性を主張して収拾がつかなくなったといいます。
数え年わずか2歳の三法師を名代とするのはその打開策であり、秀吉が提示したこの案に同意する形で信雄・信孝が後見になった経緯がありました。
信雄は信長遺領である尾張・伊賀・南伊勢にわたる約100万石を継ぎ、天正11年(1583)、賤ヶ岳の戦いの際に、秀吉に合力して柴田勝家と織田信孝を滅亡に追いやります。

しかしその後の信雄は、三法師の後見のために入城した安土城を退去させられるなど、秀吉との関係が険悪なものとなっていきました。両者の亀裂が決定的となった後、信雄は伊勢長島に戻り、徳川家康に接触して vs秀吉戦に向けた準備が開始されたのです。
羽柴秀吉vs織田信雄・徳川家康連合
天正12年(1584)3月、信雄は秀吉に内通した嫌疑で「浅井長時」「岡田重孝」「津川義冬」の三家老を処刑。これにより事実上の宣戦布告がなされたともいえるでしょう。同月、主家・織田家を救援するという大義名分のもと、徳川家康が約1万5000の兵を率いて清洲城で信雄と合流。秀吉との全面対決の態勢を整えます。信雄と家康連合は、秀吉軍に対抗するために近畿・四国・北陸・関東の広範囲にわたる諸勢力と結び、「秀吉包囲網」ともいえる布陣を構築しました。
一方の秀吉陣営も、家康同様に佐竹氏や宇都宮氏、毛利氏などの諸勢力と結びついており、さらには信長の旧重臣やその二世代目等の顔ぶれも目立っています。
以下、両陣営の主な勢力をみてみましょう。
◆ 羽柴秀吉派
- 丹羽長重
- 森長可
- 池田恒興
- 前田利家
- 滝川一益
- 宇都宮氏(下野国)
- 佐竹氏(常陸国)
- 木曾義昌(信濃国木曾谷)
- 毛利氏(中国)
VS
◆ 織田信雄・徳川家康派
- 後北条氏(関東)
- 長宗我部氏(四国)
- 雑賀衆(紀伊国)
- 根来衆(紀伊国)
- 粉河寺衆(紀伊国)
- 佐々成政(越中国)
両軍の総兵力は諸説あり定かではありませんが、信雄・家康陣営は1万6千~3万、対する秀吉陣営は8万~10万だったともいわれています。
※参考:「小牧・長久手の戦い」の主な合戦の一連の流れ
| 時期 | 小牧・長久手方面の合戦 | 周辺各地での合戦 |
|---|---|---|
| 3/17 早朝 | 羽黒の戦い | |
| 3月 | 岸和田合戦 | |
| 4/9 未明 | 岩崎城の戦い | |
| 4/9 午前 | 白山林の戦い | |
| 4/9 午前 | 檜ケ根の戦い | |
| 4/9 昼 | 長久手の戦い | |
| 5~7月 | 沼尻の合戦 | |
| 5月~6/10 | 竹ヶ鼻城の戦い | |
| 6/11 | 第二次十河城の戦い | |
| 6/16 | 蟹江城合戦 | |
| 9月 | 妻籠城の戦い | |
| 9/9 | 末森城の戦い | |
| 9/15 | 戸木城の戦い |
小牧・長久手方面の合戦
戦端は同年3月13日、織田家譜代の重臣・池田恒興が秀吉軍へと寝返り犬山城(現在の愛知県犬山市)を占拠したことで開かれました。この日は徳川方が援軍として信雄の清洲城へと入城した当日であり、家康はこれに対抗すべく、3月15日には小牧山城(現在の愛知県小牧市)に急行。臨戦態勢をしきます。
以下、時系列順に小牧・長久手方面での戦闘経緯をみていきましょう。
3月17日早朝 羽黒の戦い
池田恒興との共同戦線を予定していた秀吉方の森長可は、3月15日に美濃・兼山城を出陣。池田勢に先行する形で3月16日に犬山城南方の羽黒に着陣しました。しかしこの行軍動向は家康方に筒抜けであり、同日の夜半に松平家忠および酒井忠次率いる5000の部隊が羽黒に向けて出撃しました。翌3月17日早朝、酒井忠次の部隊が森長可隊に奇襲攻撃をかけ、段階的に松平家忠の鉄砲隊、そして酒井の分隊による波状攻撃で森長可隊は敗走。300余りの兵を失ったとされています。
森長可は織田の旧臣で「攻めの三左」の異名をとった森可成の子で、森成利(蘭丸)の兄にあたる武将です。後世「功を焦った」と評されることもあるように、独自行動を察知されての完敗という結果となりました。
3月18日 小牧での両陣構築
先鋒部隊となった森長可隊を撃破した家康は、小牧山城周辺の防御機構を拡充し迎撃態勢を整えていきます。長可敗北の報を受け取った秀吉は3月21日、自ら3万の兵を率いて大坂城を出陣。同月末までには犬山に着陣し、同市楽田(がくでん)城に拠点をおいたと考えられています。
秀吉本隊が到着するまで両陣営は陣地構築に集中し、その間は膠着状態になっていたとされています。
4月6日 秀吉陣営各隊出陣
両軍は小牧付近でのにらみ合いが続いていましたが、4月4日に池田恒興が三河侵攻を秀吉に上申。家康に小牧を放棄させる作戦を立案します。また、翌早朝には森長可とともに再度秀吉のもとを訪れ、羽黒の戦いにおける雪辱戦を願い出ます。秀吉はこれを許可し、森長可隊を中心とした部隊編成を行い、4/6に三河西部への侵攻作戦が開始されました。
その折の秀吉方の陣立は以下の通りです。
- 第一隊(池田恒興)…兵力6,000
- 第二隊(森長可)…兵力3,000
- 第三隊(堀秀政)…兵力3,000
- 第四隊(羽柴秀次)…兵力8,000(または1万6,000)
家康はこの動きを伊賀衆や近隣住民からの情報網で察知し、4月8日には在地勢力を中心とした「丹羽氏重」「水野忠重」「榊原康政」「大須賀康高」らの部隊が小幡城(現在の愛知県名古屋市守山区)に着陣。ほどなく合流した家康・信雄の主力部隊と軍議の結果、兵力を二隊に分散して各個に戦闘行動に移る作戦をとりました。
4月9日早朝、家康・信雄勢の一隊は羽柴秀次の第四隊を背後から襲うべく行軍を開始しました。
4月9日未明 岩崎城の戦い
同日未明には秀吉方第一隊の池田恒興が、岩崎城(現在の愛知県日進市)を攻撃。丹羽氏重らの守備隊は善戦するも、戦闘開始3時間余りで岩崎城は落城したといいます。この間、秀吉方第二~第四隊は現在の愛知県尾張旭市・長久手市・日進市におよぶ地帯で休息をとり、最新軍のため待機していました。
4月9日午前 白山林の戦い
この日未明、羽柴秀次隊は休息中の隙を突かれる形で、家康・信雄支隊の攻撃を受けました。背後からは丹羽氏次・水野忠重・大須賀康高らの部隊、そして側面からは榊原康政の部隊が殺到し、秀吉方第四隊は壊滅しました。隊長の秀次も自身の馬を失い、側近の馬を使って辛くも脱出したといいます。退却においては、秀吉の与力出身で秀次目付の木下祐久をはじめとした多くの木下氏一族が殿を務め、秀次を逃がすため討ち死にを遂げました。
余談ですが、榊原康政が秀吉の織田家の乗っ取りを非難する檄文を書き、激怒した秀吉が、康政の首に10万石を懸けた話は有名です。
あわせて読みたい
4月9日午前 檜ケ根の戦い
白山林の戦いにおける秀次隊壊滅の報せを受けた秀吉方第三隊・堀秀政は、急遽進軍経路をとって返し第四隊の敗残兵を救助。檜ケ根(現在の愛知県長久手市)に陣を展開して家康・信雄勢を迎撃する構えをとりました。先の戦勝の勢いにのって猛攻を仕掛けた家康・信雄支隊でしたが、堀秀政隊の反撃を受けて敗走。追撃され約300~500の兵を失ったとされています。
4月9日午前 家康、色金山着陣
色金山(現在の愛知県長久手市)に着陣した家康・信雄本隊は檜ケ根における支隊の敗走を知り、堀秀政隊が秀吉方第一隊・池田恒興および第二隊・森長可と合流できないよう、両者の間を分断するように布陣しました。堀秀政にはこの時、第一・第二隊より援軍要請が届いていましたが、「金扇」の馬印を確認して家康本人が隊を率いていることを知り、部隊を後退させることを選びました。
4月9日昼頃 長久手の戦い
4月9日午前10時頃、秀吉方と家康・信雄方の決戦が長久手において行われました。両軍の陣立は以下の通りです。家康・信雄方
- 右翼…徳川家康隊・兵力3,300
- 左翼…井伊直政隊・兵力3,000
- 織田信雄隊・兵力3,000
秀吉方
- 右翼…池田元助、輝政隊・兵力4,000
- 左翼…森長可隊・兵力3,000
- 後方…池田恒興隊・兵力2,000
両軍の戦闘は2時間あまりにおよんだとされ、前線で戦っていた森長可が銃弾を受けて討ち死に、さらに池田恒興・元助父子も白兵戦で討ち取られました。池田輝政は説得されて戦線を離脱、戦闘は家康・信雄連合の勝利に終わりました。
秀吉方は死者2500名あまり、家康・信雄方も600名弱の死者を出すという凄惨な激戦だったと伝わっています。
この間、秀吉本隊は2万の軍勢を率いて主戦場へと急行しましたが、家康・信雄隊は迅速に陣を引き払い、迂回しつつ小牧山城に帰還し追撃を許しませんでした。そのため秀吉本隊は楽田へと戻り、以後両軍のにらみ合いは続いたものの5月1日に秀吉隊主力が小牧地域から撤退。家康・信雄勢も7月中旬には退陣したとされています。
あわせて読みたい
周辺各地での合戦
小牧・長久手の戦いは先述の通り、各地で連動的に戦闘が起こった大規模な事件でもありました。以下に時系列でその概要を記します。3月~ 【関西】岸和田城合戦
反秀吉派の紀州根来衆・雑賀衆・粉河寺衆が、秀吉不在の隙に堺、大坂、岸和田城などを攻撃。中村一氏・松浦宗清らが防衛。5月~7月 【関東】沼尻の合戦
北条氏直と、佐竹義重・宇都宮国綱らとの間で合戦が勃発。佐竹・宇都宮連合側は長篠合戦を上回る8000丁以上もの鉄砲投入の準備をするも、大規模な戦闘はなく、7月22日に講和。4月8日 【伊勢】
羽柴秀長が織田信雄築城の松ヶ島城(現在の三重県松阪市)を攻略。4月17日 【美濃】
美濃東部では森長可の討ち死ににより、徳川方の遠山利景が明知城(現在の岐阜県恵那市)を奪還。6月6日 【尾張】蟹江城合戦
蟹江城(現在の愛知県海部郡蟹江町)が、滝川一益、九鬼嘉隆らによって落城。家康・信雄連合は即座に反撃、7月3日には蟹江城奪還を含む周辺制圧を完了。6月10日 【美濃】竹ヶ鼻城の戦い
秀吉方が竹ヶ鼻城(現在の岐阜県羽島市)を水攻めで攻略。6月11日 【讃岐】第二次十河城の戦い
長宗我部元親が十河城を攻略、讃岐を平定。家康・信雄ともに長宗我部・香宗我部氏に働きかけ、秀吉方を牽制。8月16日 【尾張】
秀吉が楽田城に入城。同28日に家康も岩倉城(現在の愛知県岩倉市)に入城し、両陣営の間で小規模戦闘。9月 【信濃】妻籠城の戦い
妻籠城(現在の長野県南木曽郡)を家康方の部隊が攻撃、木曾義昌重臣・山村良勝が撃退。9月9日 【能登】末森城の戦い
佐々成政が末森城(現在の石川県宝達志水町)を攻撃、前田利家の反撃で退却。9月15日 【伊勢】戸木城の戦い
戸木城(現在の三重県津市)に籠城した木造具政らの織田信雄勢が、蒲生氏郷ら秀吉方の攻撃で敗北。戦線の終息
戦国の当時において、全国規模といっても差し支えない広範囲におよんだ小牧長久手の戦いでしたが、意外な形で戦線は終息します。同年11月12日、秀吉は伊賀・伊勢半国の割譲を条件として信雄に講和を交渉、これを受託したことで反秀吉方の総大将ともいえる信雄自身が戦線を離脱しました。
これは独断での単独講和とも解釈され、このことで家康も信雄との連合を解消する形となり、同月17日に三河へと帰還しました。秀吉はその後家康との講和にも動き、家康が次男の「於義丸(のちの結城秀康)」を秀吉のもとへと送ったことで、小牧長久手の戦いは一応の終息を迎えました。
戦後、信雄・家康ともに秀吉と講和したことで各地の反秀吉勢力は宙吊りとなり、それぞれ各個に撃破されていくこととなります。秀吉はその後も家康の武力制圧を想定していたといいますが、最終的には臣下として迎えることに腐心したのは周知のとおりです。
まとめ
事実上、秀吉vs家康の大戦だったといっても過言ではない小牧長久手の戦い。寡兵ながら巧みな戦術で秀吉勢を退けた家康の強さが、もっとも際立った時期といえるかもしれません。その根底には、在地勢力や伊賀衆の力を活用した情報戦の能力に秀でていたことが挙げられるでしょう。敵部隊の動きを先読みし、その意表を突くような奇襲・分断作戦は用兵の妙技を鮮烈に印象付けています。
一方で、戦闘で押されつつも最終的に実質的勝利へと導いた秀吉の手腕も、実に巧みと言わざるを得ないでしょう。両雄が相まみえたこの戦、日本史における大きな画期のひとつだったといえるのではないでしょうか。
あわせて読みたい
【主な参考文献】
- 『日本歴史地名体系』(ジャパンナレッジ版) 平凡社
- 『国史大辞典』(ジャパンナレッジ版) 吉川弘文館
- 『ビジュアルワイド図解 日本の合戦』 2014 西東社
- 『【決定版】図説・戦国合戦集』 2001 学習研究社
- 『歴史群像シリーズ 51 戦国合戦大全 下巻 天下一統と三英傑の偉業』1997 学習研究社
- 『歴史群像シリーズ 45 豊臣秀吉 天下平定への智と謀』1996 学習研究社
- 小牧市HP 小牧・長久手の戦い


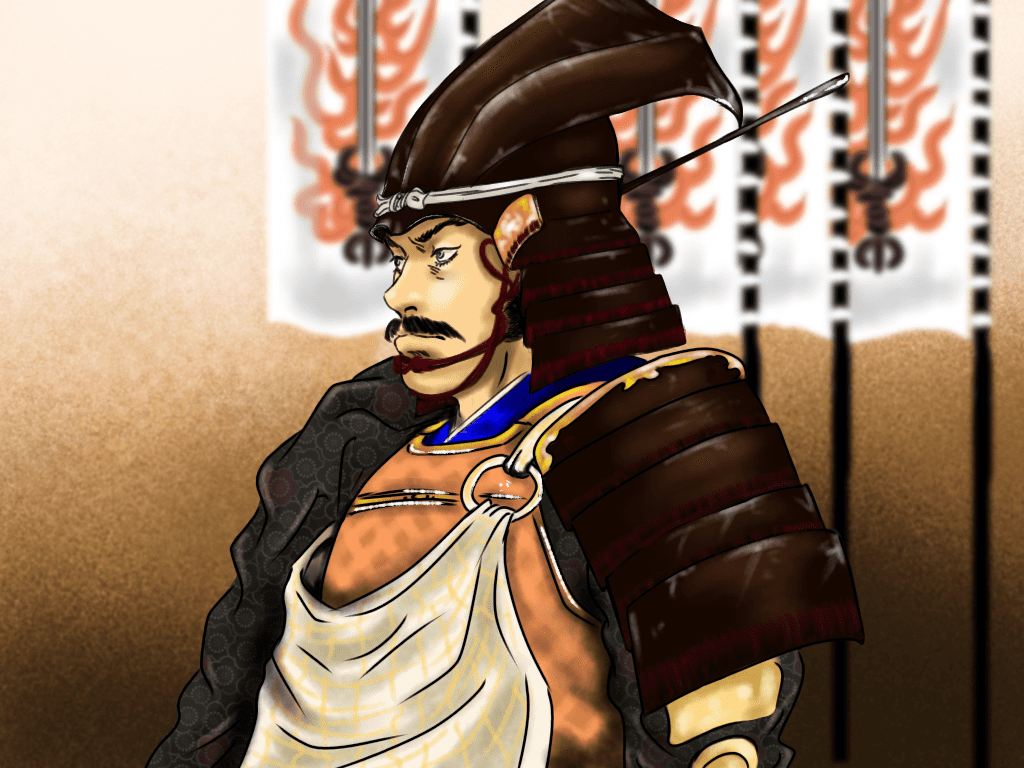



コメント欄