明智光秀の名言・逸話37選
- 2019/11/29

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
織田信長など人気の高い武将の場合は割合と逸話が集めやすいし、260年にわたる天下泰平の世を作り上げた、戦国の勝ち組である徳川家康などは逸話の宝庫と言っても過言ではないだろう。しかも勝者は話が盛られやすく、かなりポジティブな内容の逸話が多いのである。
しかし、あまりの知名度のため、もはや「隠れた一面」とか、「世間にあまり知られていない話」などというのが少なくなっているのも事実である。そして、昨今の歴女ブーム等により、その傾向はより強くなった感があり、かつては「逸話」であったものが、現在では「使い古されたネタ」位の地位までに低下してしまったものすらある。
一方、歴史の敗者についてはどうであろう。当然ネガティブな内容の逸話が多いわけであるが、敗者だけに関心が薄く、さほど調べられもせずにいるため、昔ながらの固定化されたイメージが先行していることが多いように思う。
ちょっと前までは石田三成がそうであった。戦下手の嫌味な官僚タイプというステレオタイプな人物像が固定化されていたのであるが、歴女の間で「実は義の武将だった」と人気が上昇したため、最近ではその人物評はかなり様変わりしている。
さて、それでは明智光秀はどうであろう。日本史上最強の謀反人でありながら、その人となりについてはイマイチ認知されずにいるようだ。いまだに「青白きインテリタイプで、信長の仕打ちに耐えかねてブチ切れ謀反を起こした」という認識をお持ちの方も多いと推察する。
光秀の逸話をかき集めることで、明智光秀に新たなスポットライトが当てられ、その人物像が浮き彫りとなる一助となれば幸いである。
流浪時代
光秀諸国を遍歴す
光秀は明智城落城の後の1556年~1562年に諸国を遍歴し、兵法・軍法などの武者修行を行ったという。(『明智軍記』)
中野某との約束
光秀が流浪時代、三河の牧野右近大夫に仕えた際のこと、頼りになる同輩の中野某に次のように言ったという。
「将来、わしが一国一城の主になった暁には是非城代としてお迎えしたい。貴殿のほうが出世していたら、そなたの家臣になろう。」と。
後に光秀が丹波を拝領した際には、約束通り中野を亀山城の城代として迎えたという。(『名将言行録』)
光秀大志を抱く
光秀がまだ二十歳そこそこであった頃、大黒天の像を拾ったのを見かけた家臣は「大黒天を拾うと千人の頭になれるそうです」言った。光秀はそれを聞くと、その像をあっさり捨ててしまったという。家臣がその理由を尋ねたところ、「私はその程度で終わるつもりはない」と、その大志を明かしたという(山鹿素行『山鹿語類』)
ホクロが決め手
煕子には容貌がウリ二つの妹がいたとされる。
光秀と煕子との婚約が成立した後のこと、花嫁修業中の煕子と、その妹が疱瘡を患ってしまった。妹は完治したが、煕子は顔にアバタが残ってしまい、これを恥じた煕子の父は、姉妹とも相談の上、煕子の妹を煕子と偽り、光秀のもとに嫁がせようとした。
ところが、光秀は煕子の顔にあったはずの小さなホクロがないのを不審に思ったため、妹は観念して事の次第を述べて、髪を切り出家しようとしたという。光秀はそれを押しとどめて、親元に「自分は煕子殿を妻にと決めているので、煕子殿をお送りいただきたい」という手紙を書き、無事煕子との祝言を挙げたということである。(『武家義理物語』)
毛利元就、光秀の才を見抜く
美濃を追われ、流浪していた時代に光秀は毛利元就に仕官を求めたことがあったという。ところが、元就は「才知明敏、勇気あまりあり。しかし相貌、おおかみが眠るに似たり、喜怒の骨たかく起こり、その心神つねに静ならず。」と言って断ったという(『太閤記』上和編)。
元就は光秀の才とともに、災いをもたらす激しい一面をも見抜いてしまったのだろうか。同様の逸話が『石山軍記』にも見られるのはとても興味深い。
「彼の浪人が相を觀(観)るに、主人の爲(為)に不吉の相あり。萬一(モシ)是を召し抱えたならば、一旦は武勇智謀をも顕(あらわ)し大敵をも取り拉(ひし)ぐだろうが、主人を思う事甚だ薄く、僅かの怒りに害心を挿し挟む相貌あり。」(『石山軍記』)
細川家へ仕官
光秀は若い頃細川藤孝に仕えたことがあったという。その時の六はわずかに80石であり、しかも石ばかりの荒れた土地であったらしい。光秀は家老の米田監物入道宗鑑に、もう少しよい土地に変えていただけないかと再三懇願したが許されなかった。これには光秀も大いに憤り、細川家を去ったという。(『名将言行録』)
実は、この話には後日談がある。
光秀が織田家の家臣となり出世頭となった頃のこと、細川忠興を聟として初めて忠興の屋敷に招かれた。光秀は、米田宗鑑に対面したいとの要望を忠興に言ってあったのだが、宗鑑は、かつて細川家にいた頃のことを恨まれているのではと勘ぐって、会うのは迷惑であるという態度を取っていたという。
それを聞いた光秀は、
「もし宗鑑が儂の望みを聞いておったなら、儂は未だに細川家の家臣であったに違いない。そして織田家に召し抱えられてここまで出世することもなかったであろう。それを思えば宗鑑は儂にとって福の神のようなものだと言えるだろう。」
宗鑑は驚き、それならばと、面会に応じたという。光秀は本当に常日頃から「今の自分があるのは宗鑑のおかげだ」と口癖のように言っていたということだ。(『名将言行録』)
光秀軍師として活躍
1562年加賀で浪人中であった光秀が一向一揆と朝倉景行との戦の様子を見たときのこと、一揆の不穏な動きに気付いた光秀は、「(夜陰に紛れて一揆勢が奇襲をかけてくると踏んで)ゆめゆめ御油断なされませぬように」と言ったという。
そして、明智光春、明智光忠ら鉄砲の名手を配置して一揆勢の奇襲に備えたところ、予測通り一揆勢が奇襲を仕掛けてきた。鉄砲の一斉射撃で総崩れとなった一揆勢は朝倉勢によって、壊滅的打撃を受け敗走したという。この功績により光秀は朝倉義景より感状を賜ったということだ。(『明智軍記』)
ちなみに小瀬甫庵『太閤記』にも同様の逸話がある。
朝倉家臣時代
光秀は鉄砲の名手
「一百の鉛玉を打納たり。黒星に中る数六十八、残る三十二も的角にそ当りける」(『明智軍記』)。
ここで言う「的(まと)」とは一尺四方のものを25間(約45.5メートル)離して設置したものだというから、かなりの腕前だったことになる。また、飛ぶ鳥を鉄砲で撃ち落としたという逸話も存在する。
妻は熙子1人だけで十分?
たとえ天下をとったとしても、妾は持たぬ。(『一話一言』)
光秀が朝倉家に仕えてだいぶ経った頃のこと、出仕前に身なりを整えようと鏡を見ると、鬢に白髪が生えていることに気がついた。このままでは、大志を全うできないうちに一生を終えてしまうと思った光秀は、朝倉家を去ることを決意し、妻と下人たちを連れて越前と美濃の国境の柳ケ瀬という所にひとまず逗留することにした。
逗留先の居所で知り合いを呼んでの連歌の会を開くことになった光秀は、妻の熙子にその饗応を頼んだという。
金のなかった熙子は自分の髪を切って売ることで金を工面したが、髪の短くなった熙子を見た光秀は「出家して自分を見限るつもりか」と憤ったという。
下女に事の次第を聞き及んだ光秀は短慮を詫び、「たとえ天下をとったとしても、妾は持たぬ。」と約束したという。(『一話一言』)
織田家で頭角を現す
金ヶ崎の退き口で殿(しんがり)を務める
「金ヶ崎城に木藤・明十・池筑その外残し置かれ」(『武家雲箋』)
1570年朝倉氏の金ヶ崎城攻略後、同盟を結んでいた浅井長政の裏切りが発覚、絶体絶命となった織田軍は光秀・秀吉両部隊を金ヶ崎に残し、撤退する。光秀ら殿の奮闘により、信長は無事京へ帰還したという。
延暦寺焼き打ち~坂本城主となった頃
叡山焼き打ちの中心的人物は光秀
「仰木の事は、是非ともなでぎりに仕るべく候」(九月二日付和田秀純宛光秀書状)
比叡山延暦寺焼き打ちの10日前に、光秀は雄琴の土豪・和田秀純に書状を出し、焼き打ちに非協力的な仰木の皆殺しを命じている。それまでは、光秀は比叡山焼き討ちに反対していたとされるが、この書状によって、焼き打ちの実行部隊の中心的人物であることが判明したのである。
光秀坂本の地を拝領す
「数千の屍散を乱し、哀れなる仕合なり。年来の御胸朦を散ぜられ訖。去て志賀郡明智十兵衛に下され、坂本に在地候なり」(『信長公記』)
焼き打ちの第一功労者である光秀は信長より坂本の地を拝領する。その後光秀は、この地に坂本城を築城するが、これは織田家中で「一国一城の主」第一号であったという。
坂本城築城の際
光秀が坂本城を築城したとき、三甫という人が「波間より重ね上げてや雲の峰」と詠んだのに続けて、 「城山つたい茂る松村」と詠んだという。その後、光秀は丹波亀山から愛宕山に続く山に城を築いた際に、その山を周山と名づけた。後に、人々は自分を周の武王に、そして、信長を殷の紂王にたとえたと噂したようである。(『常山紀談』)
光秀、将軍義昭に叱責を受ける
「勝龍寺細兵(細川藤孝)へ以書状・使者、連養坊知行分のこと申遣了、明十(明智光秀)へ申理義也、三太(三淵藤英)相添書状了」(『兼見卿記』元亀三年九月十七日条)
延暦寺焼き打ちに際し、光秀は何と山門関係者の所領まで押領したというのだ。またその後、『言継卿記』によると光秀は青蓮院・妙法院・曼殊院門跡領を押領している。
いずれもれっきとした天皇関係者の所領である。これには、あの将軍足利義昭もさすがに呆れたのか、光秀を叱責している。これに対し光秀は「かしらをもこそけ」(『神田孝平氏所蔵文書』)と謝罪の弁を述べているが、その後も押領は続いたという。
明智光秀と言えば品行方正というイメージがあるが、逸話によれば、かなり厚顔な一面があったことを示している。
家臣への心遣い
1573年2月将軍義昭は信長に反旗を翻す。この際、岩倉の山本対馬守らが光秀から離反しようとしたため、光秀は今堅田城を落城に追い込んだ。この合戦で、明智軍も18人が戦死。光秀は戦死者を弔うため、供養米を西教寺に寄進したという。(『西教寺文書』)
さらに、この戦で負傷した家臣への見舞いの書状が2通残されている。このような気遣いは当時極めて珍しかったようである。
長篠の合戦・丹波攻略の頃
光秀、信長を持ち上げる
1573年、武田信玄の死を伝え聞いた信長は家臣たちの前で、光秀に「信玄は実に名将であった。古今の名将はいかほどいるのか、申して見よ。」と尋ねた。
光秀は坂上田村麻呂をはじめとして、名将と評される人物の顛末を逐一述べ、最後には信長の名まで挙げたため、飯尾新七がこれを書付けた。
信長は「儂の名まで加えるとは片腹痛きこと。そういうなら、おぬしこそ天下に名だたる名将であろう。若輩ならば徳川家康、我が家臣では羽柴秀吉も名将と言うべきであろう。」と述べたという。(『名将言行録』)
主君のご機嫌取りにも抜かりない光秀の抜け目なさが窺える逸話である。
光秀、信長からもらった感状を吉田兼見に見せる
1575年5月21日の長篠の合戦後の5月24日、光秀は坂本に帰城し、吉田兼見の見舞いを受けた。その際信長からもらった感状を見せ、大層上機嫌だったという。(『兼見卿記』)
官僚的な方面だけでなく、軍事の方面でも頭角を現し始めた様子がうかがえる逸話である。
光秀茶会開きを許される
1578年元旦に光秀は信長から八角釜を拝領した。これにより、光秀は自ら茶会を開ける立場となる。この直後の1月11日に坂本城で津田宗及・平野道是・銭谷宗訥を招いて、拝領した八角釜の釜開きの茶会を開いたという。(『 天王寺屋会記』)
ちなみに、信長の嫡男信忠が「ゆるし茶之湯」の資格を得たのに続いて、この特権を与えられたのが光秀であったという。これによって光秀は織田家中において、重臣筆頭と見なされるようになったのである。
安土城天守の奉行に命じられる。
1576年、信長は安土に城を築こうとした。その際、古今の出来事に通じた光秀に意見を求めたところ、光秀は里見義弘や大内義興の城のことを述べると、「安土の城に置かれましては、天下布武の総仕上げとも言える御城ゆえ、五常五行を表して五重の天守を建られるのがよろしいかと思いまする」と細かいところまで申し上げた。
信長は大層喜び、安土城天守の奉行に任じたということである。(『名将言行録』)
光秀、兵糧攻めで丹波攻めを完遂
「堀をほり、塀・柵幾重も付けさせ、透間なく堀際に諸卒、町屋作に小屋を懸けさせ、其上、廻番を丈夫に警固を申付けられ、誠に獣の通ひもなく在陣候なり」(『信長公記』)
「はや籠城之輩、四五百人も餓死候」(四月四日付和田弥十郎宛光秀書状)
攻略が極めて困難であった丹波八上城を、光秀は兵糧攻めによって陥落させたという逸話である。兵糧攻め自体は、1516年北条早雲が相模の新井城の攻略に用いたとの記述があるため、それほど目新しい戦術ではない。光秀の兵糧攻めは、獣のはい出る隙もないという「緻密さ」の点で、それまでの兵糧攻めとは一線を画すものだったのである。
光秀、信長に称賛される
丹波国日向守働き、天下の面目をほどこし候。」(『信長公記』)
丹波攻略を成し遂げた光秀は、その功績を信長から絶賛される。そして丹波一国を拝領することとなり、近江志賀郡とあわせて34万石の大名となる。筒井順慶ら与力の石高を合わせると240万石程度に達したといわれ、この後、光秀は「近畿管領」と言うべき立場に置かれることとなる。
光秀、初心を忘れぬ光忠を称賛
光秀が福知山で父の法要をいとなんだ時のこと、焼香順は一番目が光秀、二番目が光春、三番目が光忠であった。
三番目の光忠の番が来ると、光忠は遠く離れた屏風の陰で脇差を外し、身分の低い者のするように這いつくばって焼香した。この様子を見た列席者は皆笑ったが、光秀は「光忠は父の代には我が領内の百姓であったのを、父が召し抱えて足軽としたのだ。そして、私の代になると功を重ねて出世し家老まで上り詰めたので、明智の姓を与えた。
百姓であった時の初心を忘れず、父の霊を弔ったその姿は武士の鏡とも言えるものだ。それを笑うものではない。」と諭したという。(『名将言行録』)
京都御馬揃の 総括責任者となる
「正月廿三日、維任日向守に仰付けられ、京都にて御馬揃なさるべきの間、各及ぶ程に結構を尽し罷出づべきの旨、御朱印を以て御分国に御触れこれあり。」 (『信長公記』)
1581年2月28日に信長は京で盛大な馬揃を行う。正親町天皇をはじめとして公家衆や町衆総勢20万人が見物したとされる。この大好評を博した馬揃の、いわばプロデューサーが光秀であった。
正親町天皇のアンコールにより同年3月5日にもう一度同じ場所で馬揃が行われたという。この大反響に信長は大満足だったと言われている。
しかしながら、当の正親町天皇はこの2回目の馬揃には出席していなかったという。信長と天皇の関係の微妙さも浮き彫りにする逸話である。
近畿管領となる~甲州征伐
明智光秀家中軍法を制定し、信長への恩義を語る
「自分は石ころのような身分から信長様にお引き立て頂き、過分の御恩を頂いた。一族家臣は子孫に至るまで信長様への御奉公を忘れてはならない。」(『明智光秀家中軍法』)
明智光秀家中軍法は1581年6月2日付けで発布した全18条からなる軍法である。織田家中でも初の軍法とされる。冒頭の文は家中軍法の最後に記されているが、このちょうど1年後に本能寺の変が起こると、このとき誰が予測したであろうか。
毛利攻め~本能寺の変
信長に家臣引抜を咎められる
1582年稲葉一鉄の家臣、那波直治が稲葉家を去って明智家に仕えることになった。一鉄にとっては斎藤利三に続き2人目のことだっただけに、たまらず信長に訴え出た。他家からのヘッドハンティングは当時ご法度であったため、信長は怒り、光秀を呼び出して頭を2、3度叩いたという。
光秀は「良き士を求めますのも、ひとえに信長公への奉公のためでございます。」と述べたという。信長は光秀の言い分を認め、那波直治は稲葉家に戻されているが、斎藤利三の件は不問に付されたという。(『稲葉家譜』)
人材発掘にかける光秀の凄まじいまでの執念が感じられる逸話である。
森蘭丸、明智光秀を鉄扇で打つ事
1582年5月初旬、徳川家康が上洛することとなり、光秀はその饗応役を命じられた。
光秀は大変名誉のことと思い、部屋の装飾から庭の整備に至るまで、全て抜かりなく準備を進め、誰が見ても文句の付けようがないほどであったという。
しかし、その様子を見た信長は光秀に「この度の接待の意味をどうとらえているのだ。家康にこれほどの接待をしてしまったら、朝廷から勅使をお迎えするときは何とする。」と叱責した。
家臣の居並ぶ中で恥をかかされた光秀は顔に怒りを浮かべたという。それを見た信長は「誤りを認めないとは不届きである。誰か光秀を打ち据えよ」と命じた。周りのものがどうしたものか案じていると、小姓の森蘭丸が「御上意でございます。」といって鉄扇で光秀を打ち据えた。光秀は額から出血し、屈辱に耐えながら退出したという。本能寺の変が起こったのは、それから半月ほど後のことであった。 (『絵本太閣記』)
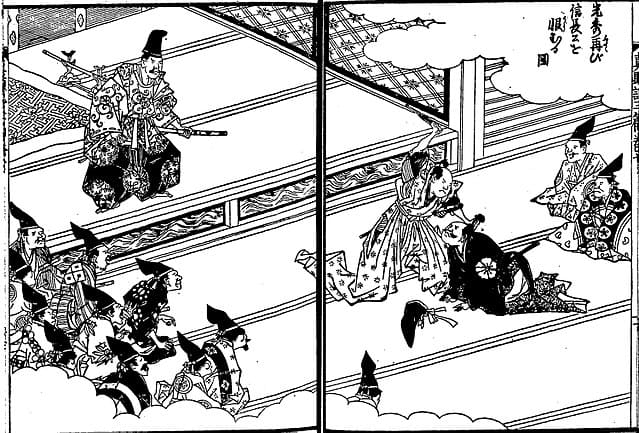
『絵本太閤記』は史料としての信憑性はかなり疑問視されているが、同様の逸話が数多く残されているところを見ると、信長との間に何らかのトラブルがあったのは本当のことかもしれない。
光秀おみくじを引く
「次の日、廿七日に、亀山より愛宕山へ仏詣、一宿参籠致し、惟任日向守心持御座候や、神前へ参り、太郎坊の御前にて、二度三度まで鬮を取りたる由、申候」(『信長公記』)
愛宕百韻に先立ち、おみくじを三度引いたという有名な逸話である。三度とも「凶」であったという逸話も残されているが、真偽のほどは不明とされている。ちなみに、三度引いたのは、当時一般的だった擲銭法によるものだったという説もあり、不安から籤を引いたという話ではないようである。
ときは今 天が下知る五月哉
亀山城出陣の直前に愛宕権現に参拝した光秀は、その翌日威徳院西坊で連歌の会を催した。(『信長公記』)
いわゆる「愛宕百韻」である。その際に光秀が詠んだ句が「ときは今 天が下知る五月哉」だと『信長公記』にも記されている。通説として解釈は「今こそ、土岐氏の人間である私が天下を治める時である」というものである。そう解釈すると、これは謀反を起こすという密かな宣言ということになる。
これを裏付けるものとしては「光秀は連歌会の卒爾に本能寺の堀の深さを問うた」(『改正三河後風土記』)
などがあるが、史実かどうかは疑わしい。
光秀謀反
信長は光秀に毛利攻めにあたっていた秀吉の援軍を命じた。
軍勢を整えた明智軍が大江坂に到着すると、兵の馬の轡を外して足軽の草履を履き変えさせた。急な戦闘準備命令に、兵は皆不思議に思ったという。桂川を渡ってところで、光秀は「私は信長公に積年の怨みがあった。今から本能寺に赴いてこれを攻めよ」と述べたという。(『武将感状記』)
いわゆる有名な「敵は本能寺にあり」のシーンである。

本能寺の変後京都の治安維持を厳命す
「 明智は、都のすべての街路に布告し、人々に対し、市街を焼くようなことは せぬから、何も心配することはない。 むしろ、自分の業が大成功を収めたので、 ともに歓喜してくれるようにと呼びかけた。 そしてもしも兵士の中に、市民に対して暴行を加えたり不正を働く者があれば、ただちに殺害するようにと命じ た」(『 ルイスフロイス日本史』)
本能寺の変後光秀が最初に着手したのは、安土城を押さえることと朝廷工作であった。朝廷の方は6月7日に誠仁親王が京都の経営を光秀に任せる旨を伝えている。京の治安維持策が効いたものと思われる。
光秀、京の屋地子を免ず
本能寺の変で信長を討った後、光秀は京の屋地子を免除した。その際、京童に対して「信長は殷の紂王であるから討ったのだ」と自らの大義を述べた。京童は地子銭が免除されたうれしさから光秀をもてはやしたが、内心は「ご自分を周の武王になぞらえるとは片腹痛きこと」と思ったという。(『豊内記』)
分け前の分配
信長が財宝を入れていた蔵と広間を開放すると、 大いに気前よく仕事に着手 し、まず彼の兵士たちに、ほとんど労することなく入手した金銀を分配した。 このようにして、信長が多大の困難と戦争により、長い年月を費やして蓄積した 物を、明智は二三日の間に分配してしまった」(ルイスフロイス『 日本史』)
味方の兵の士気をあげるべく、光秀は安土城の金銀財宝を全て分配したとされる。本能寺の変後、味方の人身掌握に努める光秀であったが、多数派工作には苦労することとなる。
山崎の合戦~敗死
藤孝は動かず
「一、我等不慮の儀存じ立て候 事、忠興など取立て申すべきとての儀に候、 更に別条なく候、五十日 百日の内には、近国の儀 相堅め候間、その以後は十五郎・与一郎殿など引渡し申し候て、何事も存ず間敷候」
(『 細川家文書』)
本能寺の変の後、光秀は与力であり、旧知の友でもあった細川藤孝に自分と軍事行動を共にするよう要請するが、藤孝は信長の死を悼んで出家してしまう。さらに、光秀の娘玉と妻としていた息子忠興も玉を離縁し、明智家と義絶してしまったとされる。
この書状は藤孝の翻意を促すため、自分が謀反を起こしたのは忠興殿を取り立てるためであると述べ、天下を収めた後には息子たちに任せ引退するつもりだという意思を伝えたものだった。しかしながら藤孝・忠興父子が光秀に与することはなかったという。
高山右近の調略
「 彼( 光秀 )はジュスタ (右近の妻 ) に対して、心配するには及ばない、( 高槻)城はあなたのものだ、と伝えさせた。 高槻の人たちは、彼に美辞麗句をもって答えた」(ルイスフロイス『 日本史』)
光秀は高山右近を味方につけようと、高槻城に向かい右近の妻に高槻城を占拠するつもりはないことを伝えた。高槻城の留守役は、光秀に対して好意的な返答をしたようである。しかし、秀吉の中国大返しの報に接するや、右近は秀吉につくことを決断する。
光秀敗走
「 哀れな明智は隠れ歩きながら、農民たちに多くの金の棒を与えるから自分を坂本城へ連行するようにと頼んだということである。 だが彼らはそれを受納し、刀剣も取り上げてしまいたい欲に駆られ、彼を刺殺して首を刎ねた」(ルイスフロイス『日本史』)
山崎の合戦に敗れた後の光秀の様子を描写したものであるが、小栗栖で落人狩りの竹槍によって瀕死の重傷を負ったという逸話とはやや異なる。
辞世の句
「順逆無二門 大道徹心源 五十五年夢 覚来帰一元」 (順逆二門に無し 大道心源に徹す 五十五年の夢 覚め来れば 一元に帰す)『明智軍記』
光秀の辞世とされる句であるが、後世の編纂物によるものという見解が一般的である。
年代不詳の逸話
実は怪力
「馬上で太刀打ちとなった時、光秀は相手の馬の鞍橋を引き切った。また、家臣が敵に組み敷かれているのを見るや、敵の兜の下部をつかんで引き倒したという。(『明智軍記』)
まとめ
いかがだっただろうか。今回は明智光秀に関して、出典が確認できる名言・逸話をできるだけ数多く集めたつもりである。その際、史料の信憑性は度外視した。なぜかというと、明らかに史実ではない記述であったにせよ、本人を知る人物のものであれば「この人ならこんな行動をとったはず」という分析の基に記述が進められた可能性が大だからだ。
人物像を浮き彫りにするという意味では、そのような記述は貴重である。そして、極力時系列に沿って名言・逸話を書いていくことで、光秀の成長の様子も読み取れるという狙いもあった。このような手法を採って書いていると、なんだか自分が歴史小説を書いているような気分になってくるから不思議である。
光秀の若い頃の逸話を読むと、意外にも野望大にして短気であり、短慮ですらあることがうかがえる。戦ではどちらかというと勇猛果敢である。ところが、織田信長の家臣となってからは、持ち前の緻密さも発揮するようになる。
信長の徹底した能力主義・合理主義が光秀に与えた影響は、かなり大きいのかもしれない。光秀が信長に感謝している逸話もかなり残されているが、これはポーズではなく心底そう思っていた可能性は高いだろう。
【主な参考文献】
- 橋場日月『明智光秀 残虐と謀略 一級史料で読み解く』(2018年)
- 樋口晴彦『新視点から見た本能寺の変』(Panda Publishing、2018年)
- 歴史読本編集部『ここまでわかった!明智光秀の謎』(歴史読本編集部、2014年)
- 小和田哲男『明智光秀と本能寺の変』(PHP研究所、2014年)
- 太田牛一『信長公記』(角川ソフィア文庫、2002年)
- 松田 毅一訳『完訳フロイス日本史』(中公文庫、2000年)



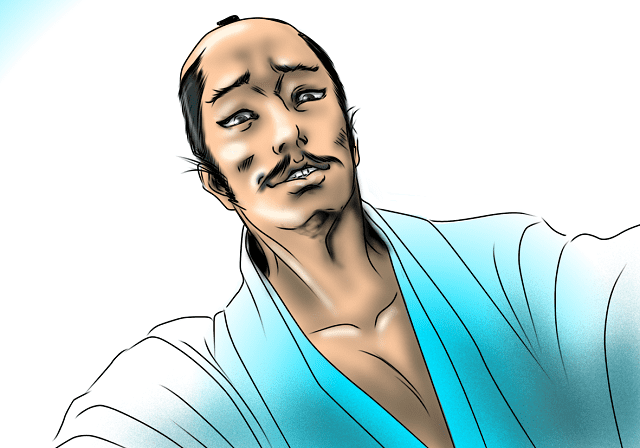

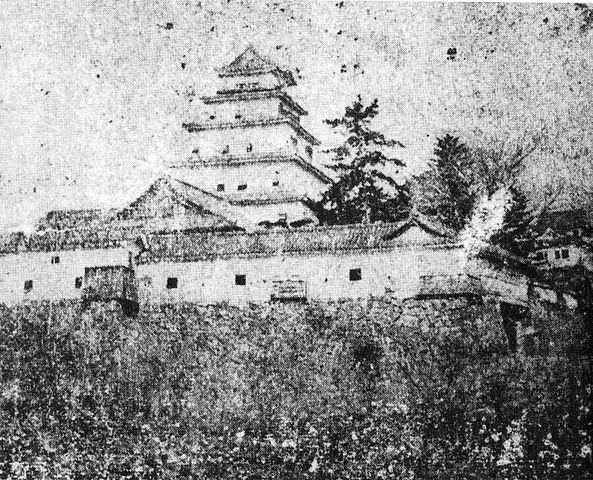
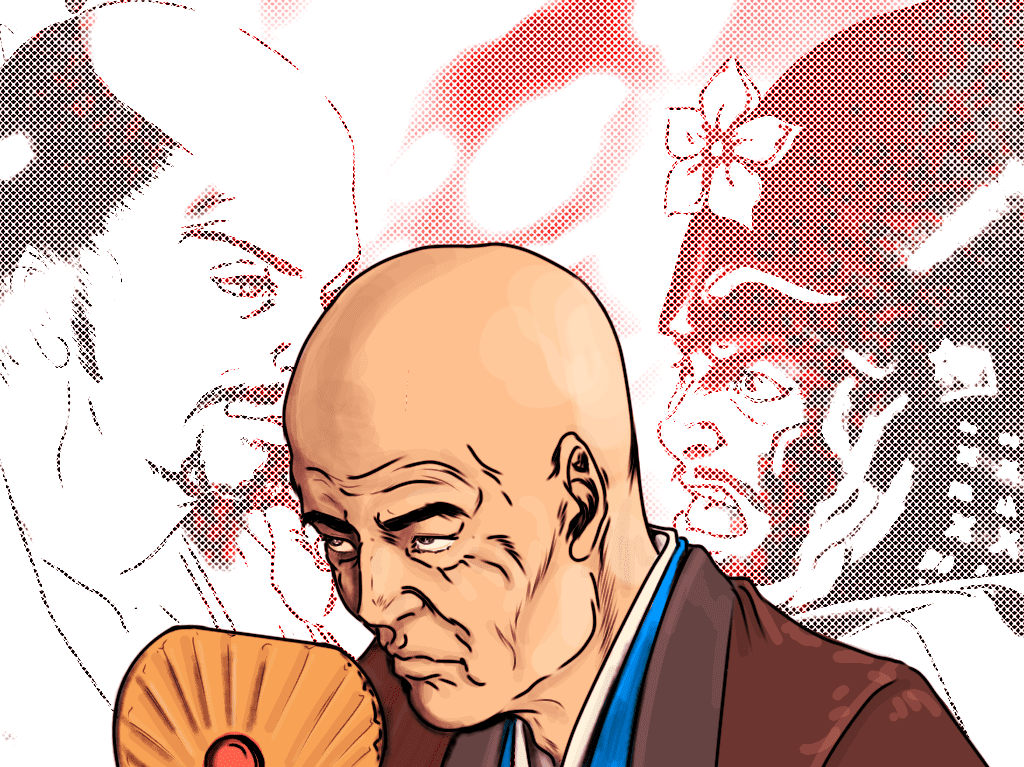
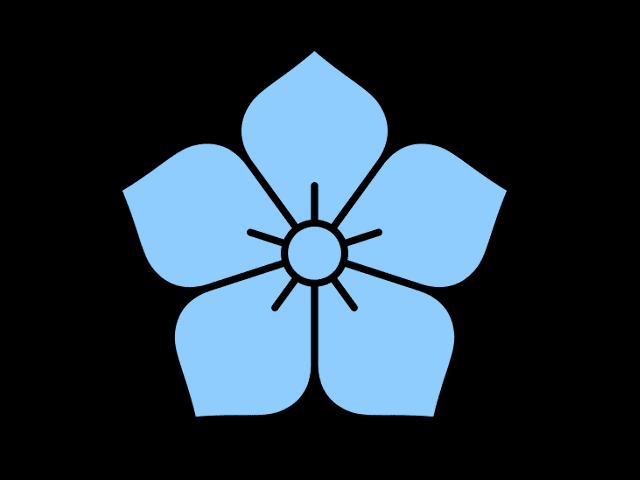



コメント欄